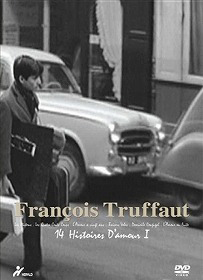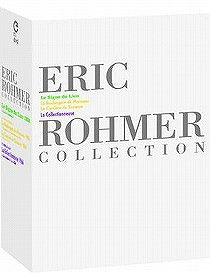海外版DVDを見てみた 第6回『ラウール・レヴィを見てみた』 Text by 吉田広明
製作作『素直な悪女』~ヌーヴェル・ヴァーグのお先払い
『素直な悪女』は、冒頭のシネスコによるバルドーの腹ばいになった全裸がスキャンダラスな関心を呼び、また彼女が激しいマンボを踊る場面などもあいまって、バルドーを一気にフランスのセックス・シンボルに押し上げる。この映画がヌーヴェル・ヴァーグの先駆のように見なされることもあるが、それはこの映画のそういったスキャンダラスな意味での新しさに加え、やはり製作者レヴィも監督ヴァディムも、何本か既に出演作はあるとはいえ、これまでにない役柄を演じたベベも含め、初めて自分の映画を撮るのだ、というその心の弾み、躍動が、何か新しいものが出現したという印象を与えたのだろうという気がする。トリュフォーはこの映画を、「個人的な日記や覚え書のような親密感にあふれたすばらしい映画」として評価している(『わが人生 わが映画』たざわ書房、P.31)が、この評はまさにトリュフォーの最もすぐれた作品群にそのまま当てはまるものだ。個人的な感情(この場合、ヴァディムのバルドーへの愛情)をそのままぶつけた監督個人の映画という意味で、映画は監督のものというヌーヴェル・ヴァーグ的な映画観に近いものがあるということもある。『素直な悪女』の企画が持ち上がった当初、レヴィは「ほとんど無一文」であったというが、「ハッタリと押しの一手であちこちの資産家を口説きまわ」って資金をかき集めた(上掲山田書P.420)。これがヒットするとレヴィは「俺は奇跡の映画を作った。莫大な金もうけのできる偉大な映画だ。今後はだれもがこうした映画を手がけることになるだろう」と豪語したという(同上、P.421)が、実際これまでにない傾向の独立製作映画がヒットしたことは、独立製作の個人的な映画が興業的にもいけるのだ、という自信を与えることになり、ルイ・マル(『死刑台のエレベーター』57)やジャック・タチ(『ぼくの伯父さん』58)などと共にヌーヴェル・ヴァーグへの援護射撃となったことは確かだろう。57年にはシャブロルの第一作『美しきセルジュ』、58年にはリヴェットの第一作『パリはわれらのもの』とアラン・レネの第一作『ヒロシマ、モナムール(二十四時間の情事)』、59年にはトリュフォーの第一作『大人は判ってくれない』、ロメールの第一作『獅子座』、ゴダールの第一作『勝手にしやがれ』が公開、とヌーヴェル・ヴァーグの烽火が次々と上がることになる。
レヴィは自身を「十九世紀の人間」と称していたというが、口八丁手八丁の山師である一方で、(遅れてきた)ロマンチストであった彼は、二十歳も年下の女性への叶わぬ愛に絶望し、猟銃自殺する。その女性はゴダールの「信奉者」(山田『ゴダール、わがアンナ・カリーナ時代』P.362)で、『彼女について私が知っている二、三の事柄』(67)ではセカンド助監督、同時に撮られていた『メイド・イン・USA』(67)では端役出演もしているが、レヴィは彼女につききりで、ゴダールの現場にいた。『彼女について』はレヴィの製作作品でもあり、アメリカ人の客をカメオ出演で演じている。