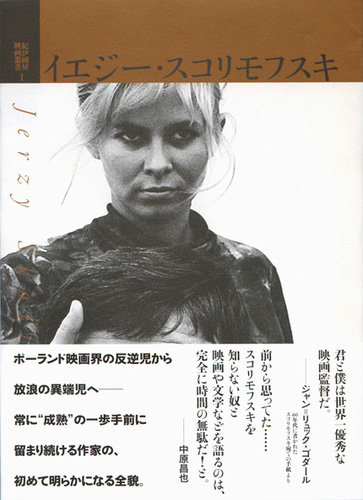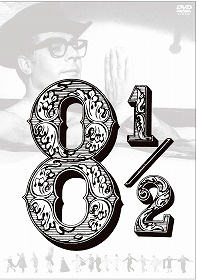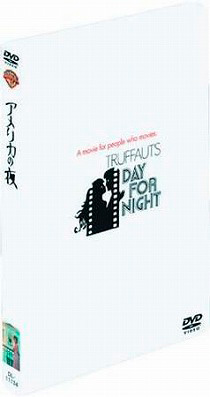映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第50回 ポーランド派映画とジャズ 後編・オラシオさんのリスニングイヴェントに参加して
第50回 ポーランド派映画とジャズ 後編・オラシオさんのリスニングイヴェントに参加して
ボグミウ・コビェラのポーランド映画史的位置
コビェラがズビグニエフ・ツィブルスキと共に学生劇団「ビム・ボム」の出身で、この二人が「ポーランド派」を代表する俳優として60年代をけん引してきた、という話題にも前回触れてある。今回はその続きから始めよう。改めてコビェラのフィルモグラフィを調査すると50年代半ばから精力的に映画に出演していることが判明したのだが、これらは日本で公開されておらずタイトルも私では翻訳できないのでパス。最初の注目作がムンクの『エロイカ』における「ダベツキ中尉」役。後半「オスティナート・ルグーブレ」パートに登場する。しかし何と言ってもコビェラの名前が一躍知られることになったのは58年の『灰とダイヤモンド』(監督アンジェイ・ワイダ)における「町長秘書ドレヴノフスキ」役だろう。実は今回、この傑作は何度も見ているのでスルーしてしまったが、フィルモグラフィを見直したら彼の名前がちゃんと載っていて「やっぱり!」と思った。町長主催のパーティーをめちゃくちゃにしてしまう酒乱の小心者がコビェラに決まっている。主人公マチェックを無駄死にさせるきっかけを作るのも彼。マチェックに扮して人気俳優となったツィブルスキとコビェラは同僚だったわけだから呼吸もぴったり。当然である。そうは言っても今日、一般的に「ポーランド派」人脈を概観する時、監督ワイダと俳優ツィブルスキを中心に置く文脈は容易に作るのが可能だが、コビェラをその中に位置づける試みはまだ少ない。
そして彼の代表作と言える『不運』が60年の製作。ムンクとコビェラが共にユダヤ系で、彼らの民族的出自の共通性が映画のキーポイントになっていることも既に記してある。ムンクは61年に事故死してしまうので、コビェラとのコンビ作はこれ以後作られることもなかった。残念。フィルモグラフィをさらに読んでいくと『サラゴサの写本』(65)にも出演していた。役名「トレド氏」で、しかしどんなキャラクターだったか思い出せないからスルーして、次の注目作はスコリモフスキの『手を挙げろ!』になる。撮影は67年だがスターリン批判とみなされて当時上映されず、そういった事情を抽象的に説明する新たなフッテージ他が加えられて81年に上映されたのが最初の公開である。コビェラは五人の主要キャラクターの中の一人で、愛称ヴァルトブルク。彼らは全員本名ではなく、彼らの所有する車の名前で呼ばれている。ヴァルトブルクは旧東ドイツ車とのこと。スコリモフスキも主人公の一人で愛称はセルビア車のザスタヴァ。「紀伊國屋映画叢書1 イエジー・スコリモフスキ」(編集:遠山純生)には本作の内容と共に「撮影風景」ルポルタージュも掲載されている。それがちょうどコビェラとスコリモフスキの出演場面なので監督としてのスコリモフスキの演出の様子と、二人の演技の成り立ちも同時に分かりとても面白い記事になっている。
コビェラの出身劇団「ビム・ボム」がグダンスク拠点であるのに対して、同書作品解説を読むとスコリモフスキはワルシャワ拠点の「学生風刺劇団」(前回「学生風刺劇場(STS)」の名前で紹介してある)で舞台に立っていたことがあるそうだ。ただし「スコリモフスキにとっては『知的、政治的に過ぎる』と映っていたとのこと」とある。以下引用。
本作はそもそも戯曲として発想されていた。そのためか、ほぼ限定された空間で展開する儀式的な対話劇は、舞台のそれを思わせるものがある。もっとも、スコリモフスキと彼の共同脚本執筆者アンジェイ・コステンコが、何らかの既存の演劇形式を意識していたか否かは不明である。(略)“学生風刺劇団”以上にスコリモフスキが愛着を覚えていたのが(略)“ビム・ボム”だという。スコリモフスキによれば、「“ビム・ボム”には純粋な美学があった。例えば墓の上で目覚まし時計が鳴る、素晴らしく抽象的な暗転とか。たぶん何も意味してなどいなかったんだろうけれど、たいそう超現実的でね…」とのこと。
喜劇俳優としてのコビェラがワイダとは『灰とダイヤモンド』で、ムンクとは『不運』で最上の表現を見せてくれた以上に、スコリモフスキとの『手を挙げろ!』ではどこか近親憎悪を感じさせるまでの親密さが表出されていたようだ。ちなみに「紀伊國屋映画叢書1」の裏表紙に石膏まみれでスコリモフスキと共に映っているのがコビェラである。スコリモフスキは本作の上映禁止措置をきっかけに国内での映画製作から撤退してしまい、コビェラとのコンビもこれ一本に終わる。これまた残念至極。ワイダとはその後も縁があり68年にはテレビ作品『レイヤー・ケーキ』に主演。原作スタニスワフ・レムのSFテイストの作品で役名は「カーレーサー、リチャード・フォックス」である。
この間コビェラにとって、というよりポーランド映画にとっての痛恨事が一つ起きてしまった。67年ツィブルスキの列車事故死である。コビェラによる盟友回想が今回の映画祭パンフレットに載っているので丸ごと引用しておく。
彼は学生劇団“ビム・ボム”の主力として活躍した。芸術監督としてアイディアと創意に満ちていただけでなく、意外に思われるかもしれないがまとめ役としても素晴らしい能力を発揮したんだ。あの小劇団は苦しい状況に置かれていた。財力のあるスポンサーもついていなかったし。ズビシェク(ツィブルスキの愛称)は休みなく働き、飾りつけをして小道具を配置した――僕らはみんな、彼の熱意に感化されたのさ。ズビシェクは妥協しない芸術監督で、そこにいるだけでみんなに刺激を与えた。長いこと彼は宿なしだった。人生の半分を列車の中で過ごしていたんだ。
ツィブルスキの死からインスパイアされたワイダの『すべて売り物』(68)には「ボベク(ボグミウの愛称)」役で登場。この映画に関しては「ポーランド映画史」(マレク・ハルトフ著、西野常夫、渡辺克義訳、凱風社刊)から引用させていただく。
映画はツィブルスキの名前こそ出てこないが、彼の伝説と、ヒーローの死後に残された伝説の余韻といったものを題材としている。(略)『すべて売り物』は、ツィブルスキというよりも、ワイダ自身、あるいはワイダの映画に出演する俳優たち、そしてワイダの他の映画について語り、またワイダの将来の芸術的展望の不確かさ、といったものについて語る作品である。(略)映画には、(略)実在の人物、ツィブルスキとワイダの友人たちが実名で登場する。この映画は、ツィブルスキを知る人々の記憶を透して彼を理解する試みであるが、最終的には、真の姿を再創造することは不可能であることを伝えるものとなっている。(略)人生のあらゆる要素は、それが死であろうと芸術上の危機であろうと、芸術に転化することができる。フェデリコ・フェッリーニの『8と二分の一』(63)やフランソワ・トリュフォーの『アメリカの夜』(73)と同様、『すべて売り物』は、創造の過程に関する自己内省的な表現主義映画、「映画内映画」である。
つまりここでのコビェラはワイダの世界観、芸術観によって濾過されたコビェラ自身を演じている。本作を私は見ていないので彼のフィルモグラフィにおいて『すべて売り物』がどのように位置づけられるものか、具体的な私の批評として語ることは出来ない。69年にはレオン・ジャノ監督『アパートメントと一人の男』に「医師トマシュ・ピエチョツキ」役で主演。これは日本未公開だが「コビェラの喜劇演技の真骨頂」という評価がIMDbで読める。 しかし既述『手を挙げろ!』が封印を解かれ十四年の歳月を経て初公開なった際、新フッテージにはコビェラの演技は見られず後ろ姿だけの出演である。実はこれは吹き替えであり、彼は既に69年に交通事故死していたのであった。この69年という年は4月にクシシュトフ・コメダが、また8月にはポランスキーの夫人シャロン・テートが不慮の死を遂げており、ポーランド映画には災厄の年というしかない。この災厄はツィブルスキの死からの一続きのものであったとも言えそうだ。