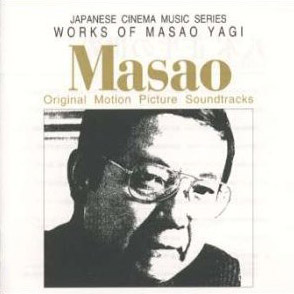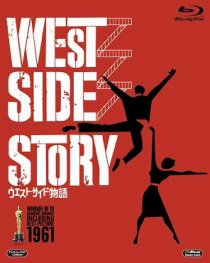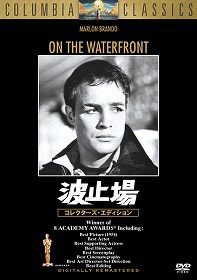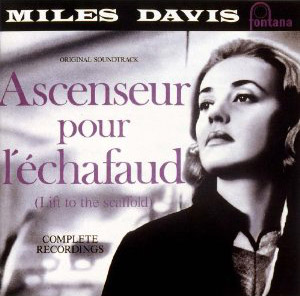映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第42回 60年代日本映画からジャズを聴く その4 八木正生とその時代(ちょい大げさ)
第42回 60年代日本映画からジャズを聴く その4 八木正生とその時代(ちょい大げさ)
八木自ら語る映画音楽のキャリア
八木の映画音楽家としてのキャリアにおいて『涙を、獅子のたて髪に』はターニング・ポイントである。「映画の仕事始めてまだ10本たらずの頃だったんですが、僕が映画の音楽って面白いなと思った、きっかけになった作品です。つまり、それまでは自分はジャズのミュージシャンでジャズを映画に使う時は…みたいな気持あったんだけど、ジャズということを離れて、映画の音楽って面白いなと思ったわけです」と「八木正生の世界」(東宝ミュージック、ポリスター)のインタビュー(インタビュアー貝山知弘)で八木自身答えている。「それから最初に出会った手ごたえのある画面でもあるわけです」とも。コンピレーション・サントラ・アルバムにも最初に収録されており、本作への八木の強い思い入れが言葉の端々から伺える。「僕にとっては色々な意味があって、トップに持って来たというのもその辺なんです。ジャズっぽいものもあるんですが収録したのはタイトルバックの甘いメロディで、棒は芥川(也寸志)さんなんですよ。とにかく映画創るって熱気がありましたよね。武満さんとやったのもこれが最初で、ここは甘く行こうとか、ここはドライに行こうとか打ち合わせしてやったんですけど、タイトル書いちゃった方がモティーフ決めちゃうみたいな雰囲気あるでしょ。この後でやった、ここには入れてないんだけれど『日本脱出』(吉田喜重、64)なんかは武満色が強いし僕も武満さんに近づけて書いたりしたけど、これは僕の色合いの方が強かったんじゃないかと思いますね」。八木が語るようにキーワードは幾つもある。まず武満徹。芥川也寸志。非ジャズ。この三つである。それぞれ後述するつもりである。「僕の本質はこういう甘いメロディなんですけど誰も理解してくれないんで困るんです。甘いメロディ好きなんです。テレるけど…」。
本作について篠田正浩は「武満徹全集」(小学館)収録の秋山邦晴との対談(初出キネマ旬報)で別な角度から語っている。これは当時人気絶頂のロカビリー歌手、藤木孝の主演。加賀まり子の映画デビュー作でもある。「港湾労働者の稼ぎをピンハネするチンピラの愛と青春を切なく謳い上げていく」と作品解説にある。「(篠田)ここまで松竹にサービスして、ぼくの松竹でのアリバイをつくったわけだから、だから、ここからはまた私のことをやろうと、そう思っていたわけです。(略)『へえ、ミュージカル映画をつくるの? 日本でね…』っていうわけですよ。そこで、武満徹ともしばらく間があいていたので、『武満さん、もうそろそろ、また松竹で映画音楽をやらない? ミュージカルなんだけれど…』といったら、『えっ!!』ってびっくりしてね」。「それで武満もプロデューサーが若槻繁氏ならば、そんなにひどい映画にもならないだろうということで、ぼくのこの仕事を引き受けてくれたと思うんですよ」。
ミュージカル映画とは言ってもハリウッド調の純度の高いミュージカルではないが、当時の日本の映画関係者にとっては『ウエスト・サイド物語』"West Side Story"(ジェローム・ロビンス、ロバート・ワイズ共同監督、61)ショックの余波冷めやらぬ時期でもあり、このカップルにはちゃんと「ロミオとジュリエット」的なテイストもある。また港湾労働者のコミュニティでの恋愛という舞台背景からは『波止場』"On The Waterfront"(監督エリア・カザン、54)のマーロン・ブランドとエヴァ・マリー・セイントを思わせる部分も見受けられる。それでどちらの映画も実はレナード・バーンスタインの音楽。「ウェストサイド・ショック」とは映画音楽関係者には「バーンスタイン・ショック」でもあったわけだ。この二本は割とたやすく今でも映画は見られるが、本稿的にはバーンスタインが指揮してキリ・テ・カナワとホセ・カレーラスが主演コンビを演じたアルバム「ウェスト・サイド・ストーリー」"West Side Story"(ポリドール)を挙げておこう。これには「映画『波止場』からの交響組曲」"Symphonic Suite from the film On the Waterfront"も収録されていてお得盤。それからもう一枚、ジャズに映画音楽にと大活躍中の作編曲家デイヴ・グルーシンがフィル・ラモーンと組んで作ったアルバム「ウェスト・サイド・ストーリー」"West Side Story"(N2K)も。アレンジはグルーシンを中心にドン・セベスキーやトム・スコットが担当しており、参加メンバーもマイケル・ブレッカー、リー・リトナー等ゴージャス。
「(篠田)そのときに、武満は『ぼくだって、歌はつくれるよ。だけど、ロックとなるとロックの専門家がいいと思う』といって、八木正生との共作という話になったんです。武満徹と八木正生というコンビ、それに芥川也寸志が指揮棒を振るという豪華メンバーによる『涙を、獅子のたて髪に』となる(略)」。「(秋山)八木正生の役割は、実際にはどのようなことだったの?」「(篠田)武満はそれ以前から八木正生のジャズ・ピアノに惚れ込んでいて、よく武満のメロディをあちこちで録音するときに、かれが現れて、ピアノを叩いているという風景をぼくは目撃していたわけですよ」。ここまでで武満と八木の基本的な関係は了解されるだろう。だがその後でちょっと気になることが述べられている。「(篠田)八木君は当時いろいろあって、かれを正業につかせなければ、という武満の友情があったんじゃないでしょうかね(略)」。「寺山修司の作詞で、藤木孝のためのロック・ヴァースを八木正生が作曲したり、武満が書いたり、これはなかなか見ものの音楽だったわけですよ。要するに、これがぼくのプレスリー・ショックというものを、もう一度、映画でやりたいというものだったんです」。後半部はわかる。気になるのは前段の「当時いろいろ」の部分で、この件については次回述べたい。
八木正生と映画音楽の関わりをここで時間軸に沿って見ていこう。
彼の最初の映画音楽は「新東宝の写真で『日本ロマンス旅行』というんです」と「八木正生の世界」インタビューで自身述べている。「マイルス・デイヴィスが『死刑台のエレベーター』でやったみたいなことがやりたいと、石井監督が考えたんだと思います。ですからジャズ・ミュージシャンにラッシュ見せてやらしたらどういうことになるかという試みだったと思います。」
この『日本ロマンス旅行』は大蔵貢が製作・原作・総指揮にあたった十話(十監督)オムニバス作品で、石井はその一人。他は中川信夫、近江俊郎、毛利正樹、等で福間健二は「新東宝後期の番線にレギュラー的に登場していた監督の陣容」とまとめている。中川信夫はこの五月、シネマヴェーラ渋谷で大々的な特集上映が組まれていて映画ファン必見だが、この映画は予定されていないのであしからず。それで石井篇の内容は『札幌篇』だから当然クラーク博士の「少年よ大志を抱け」というメッセージがテーマであった。当然、と書いたがこの映画を見ているわけではないので、このあまりに直球なメッセージがどう処理されていたかはわからない。解説によると「乱れた札幌農学校をキリスト教で矯正し」とあり、「乱れた」がキーかも、と勝手に推測するしかない。正式クレジットでは音楽担当渡辺宙明となっており、当然「石井輝男映画魂」もそうした視点からのインタビューになっている。そのために少し勘違いも生じているのだが、この件は次回にしよう。
ダビングは完全即興というわけではない。「ラッシュ見せて頂いてどういう風にするか決めて、もちろん即興の部分も多いんだけど、ここはこういうテキストを元にしてやろうということは一応決めてやりました。とにかく録音がひどいんで、びっくりしましたね。(略)その時に自分で出した音が、別の意味をもってくるでしょ。そういう音楽の機能の仕方みたいなことが非常に面白かったですね」。しかし映画、あるいは映画音楽にも当時はほとんど興味を持っていなかったとも語る彼である。「ジャズを初めて3、4年は、他のことはあまり考えなかったんですよ。(略)そのうち、武満(徹)さんと知り合いになって、彼が映画の仕事をしていたんで、時々、のぞいたりしているうちに、面白そうだって思い始めたんです」。以下次回。