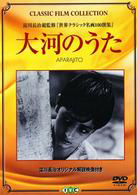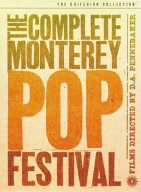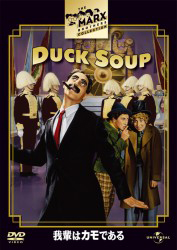映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第70回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼その8(最終エピソード)
第70回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼その8(最終エピソード)
『モンタレー・ポップ』DVD
モンタレー・ポップのラヴィ・シャンカールとジミ・ヘンドリックス
昨年亡くなった邦楽の人間国宝、尺八奏者山本邦山の仕事を八回にわたり振り返ってきた。本連載の偏った興味から、取り上げるのはジャズとの関係に限定されるものの、「現代のジャズ」(限定的な「モダン・ジャズ」という意味合いでなく)という音楽の振れ幅の大きさが反映して、イージー・リスニング・ミュージック「琴 セバスチャン・バッハ大全集」(BMGJAPAN)からフリー・ジャズ「無限の譜」(ユニバーサル)まで雑多なジャンルの邦山音源を紹介することが出来た。また現代の音楽ジャンルにおいてインプロヴィゼーション(即興)の持つ比重、という風に視点をズラすことで「即興音楽としての」民族音楽と邦楽とジャズ(ブルーズ)という関係性を提示することも出来たと思う。現在最も活き活きと即興演奏が行われているのは原則このジャンルの音楽だけなのだ。邦山がラヴィ・シャンカールのシタールを初めて聴いてから、実際彼と共演するまでに二十年を要した、と前回のラストに記した。この二十年が即ち邦山の尺八音楽の深化であったのは見やすい。師、唯是震一に導かれて邦楽界から一歩外に(ただしあくまで邦楽奏者として)踏み出した邦山の音楽的武者修行の旅程が彼のジャズとの関係の基本であった。ところで本連載に想定される読者層においてラヴィ・シャンカールはどういう存在であろうか。そういう人のことは全く知らない、という方はともかくとして、ある程度の音楽的知識を持っていれば、彼がインドの伝統音楽を世界に広く紹介するのに最も貢献した民族音楽家、シタール演奏家だということは承知しているだろう。というか実は私自身だいたいこの程度。けれどもよくよく考えてみればインドだって相当広いわけで、我々が「インド音楽」と一言でくくってしまう時にその多様性が全く考慮されていないのは明らかだ。だからここではその音楽的側面を十全に認識した上で問題にしているのではなく、あくまで彼の音楽が外界と触れあうその接触面においてのみを扱う、ととりあえず記しておく。その際、やはり最初に捉えておかねばならないのは「映画音楽家」としての側面であろう。ひょっとすると彼の音楽が日本で聴かれた最初はこの分野だったりするのではないか。そちら方面の初期代表作『大地のうた』“Pather Panchali”(55)、『大河のうた』“Aparajito”(56)、『大樹のうた』“Apur Sansar”(58)からなる『オプー三部作』“Apu Trilogy”を挙げておく。サタジット・レイ監督との名コンビである。
またジャズ関連では娘がジャズ・ヴォーカルのノラ・ジョーンズ、というのも有名な話。異母妹は、父と同じくシタール奏者のアヌーシュカ・シャンカールである。彼女のアルバムとして一枚「水の歌」“Breathing under Water”(EMI)をタイトルだけ挙げておく。何と父と娘姉妹の三人共演(同一曲共演はない)というゴージャス盤だ。しかし今回取り上げたいのはあくまで「東洋の民族音楽」が「現代の音楽(ポップスを含む)」と触れあったその接点への興味、という限定的観点によるものであり、作品は映画『モンタレー・ポップ』“Monterey Pop”(監督 D・A・ペネベイカー、67)に限られる。
本作は現在、最初劇場公開された本編に幾つかの派生短編映画や本編未収録映像、監督インタビュー等を含んだ「完全版ボックス」としても発売されているが、色々と話題が大ごとになるのでそちらには言及しない。ただしこの四月公開決定の映画『JIMI:栄光への軌跡』“JIMI: All Is By My Side”(監督・脚本 ジョン・リドリー、2014)との関連性にだけは触れておこう。このリドリー作品は伝説的なロック・ギタリスト、ジミ・ヘンドリックス誕生の瞬間に焦点を当てたコンセプト。彼は70年に人気の絶頂で亡くなってしまうのだが、66年、売れないバンドのバック・ギタリストだった「ジミー・ジョーンズ」が改名し、「ジミ・ヘンドリックス」としてアメリカで人気に火が着くまでの二年弱を描くその物語のラスト、アメリカの空港に降り立った彼の向かう先が67年の「モンタレー・インターナショナル・ポップ・フェスティヴァル1967」、通称モンタレー・ポップなのである。
その舞台の様子は従って映画には現れないのだが、興味を持った方はペネベイカー作品をご覧いただきたい。もちろんジミの素晴らしいステージも聴いていただきたい。いただきたいのだが、本連載の興味から述べる必要があるのは彼の「ワイルド・シング」“Wild Thing”ではなくて、実は最後に登場するグループの方だ。それが映画『JIMI:栄光への軌跡』では一言も語られていないラヴィ・シャンカールの演奏なのである。このライヴ音源も本当は“Ravi Shankar: Live at the Monterey International Pop Festival”としてCDになっているのだが、どうやら日本では出ていない模様。輸入盤で探して欲しい。映画でも何と20分近い時間の演奏が収録されていて、これは例外的な長さなのだが、CDではさらに映画に紹介されなかった演奏まで聴くことが出来る。
調べてみたら、この映画が日本で劇場公開されたのは77年、サトウ・オーガニゼーション配給によるものが最初らしい。私もそれで見ている。ただし見たのは79年頃だったか。新宿の厚生年金会館の裏にあった定期的な上映スペースで、ここではマルクス兄弟映画『我輩はカモである』“Duck Soup”(監督 レオ・マッケリー)、フレッド・アステアの『スイング・ホテル』“Holiday Inn”(監督 マーク・サンドリッチ)なんていう古典的な映画からケネス・アンガーの全作品、それに『パワーズ・オブ・テン』“Powers of Ten”(監督 チャールズ・イームズ)の白黒試作品等という珍品まで見ている。
ではあるが、こと『モンタレー・ポップ』に関しては、ここで見たのは二回目であり、最初に見たのはNHK総合テレビで75年の夏の終わりの午後だった。この頃NHKでは不定期で洋楽の音楽ドキュメンタリー番組「ヤング・ミュージック・ショー」を放映していて、その一環だったはずだ。番組解説者は渋谷陽一。本編の始まる前に現れてひとくさり、例の口調でさらさらっと見どころを語る。彼はこの時期NHKのFMで別にレギュラーMC番組を持っていて、何回かにわたってジミで特集を組んでいた。ある日ラジオで渋ヤンいわく「ジミがギター燃やしちゃうからテレビ絶対見てね」とのことだったんで勢い込んで鑑賞に及んだわけだが、私がノックアウトされてしまったのはジミの後で出てきた(実際の順序とは異なるのだが)ラヴィ・シャンカールのグループだったのだ。演奏の最中、客席に寝転んでいるジミの姿も捉えられているのに注目。ついでに言うと、この日この番組を見た人は日本全国で当然相当な数であって、その中に忌野清志郎もいたらしい。有名な「愛しあってるかい」という彼の決めフレーズは、この映画でオーティス・レディングが「愛しすぎて」“I’ve Been Loving You Too Long”を歌う際に聴衆に語りかける時に出たものだ(というかそのように字幕で出る)。
ラヴィ・シャンカール・グループの演奏から、清志郎のように直接影響を受けた有名人は知らないが、私のようにビックリ仰天した子供(高校二年だった)は確実にいたはずだ。そうした日本における事態は70年代後半以降というタイムラグを負っているわけだからとりあえずこれ以上は語る必要を認めないが、ライヴが行われた67年に時間をたどり返してみれば、成熟の途上にあったアメリカン・ロック・カルチャーに何よりショックを与えた点で大きな意義を持つものだ。「ショック」という言葉は便利だがあまりに雰囲気的かもしれないので改めて言い換えると、それが即ち「民族楽器(シタール)による即興演奏」の作り出す音楽的スリルなのである。そしてこの西海岸における民族音楽ショックから一週間後7月2日、大陸の反対側東海岸で行われたニューポート・ジャズ・フェスティヴァルで聴衆にショックを与えたのが、民族楽器尺八で即興演奏を繰り広げた山本邦山だったのだ。