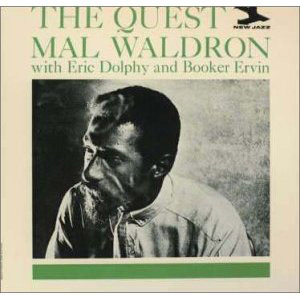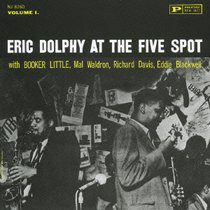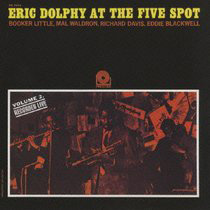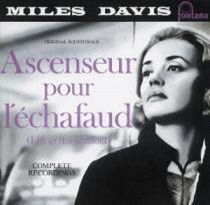映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第36回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その2 クラーク、ワイズマン、そして『クール・ワールド』(前回の続き)
第36回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その2 クラーク、ワイズマン、そして『クール・ワールド』(前回の続き)
楽曲分析とその周辺事情
ライナーノーツでフランシス・デイヴィスはこの映画音楽の特質をこう規定している。「シャーリー・クラークはマル・ウォルドロンにも(撮影のベアード・ブライアント同様)思いのままにやらせた、そして彼のつけた音楽は映画ファンには驚きをもって受けとめられたに違いない、というのもこの音楽は映画に出てくるギャングのメンバーが喜んで聴くようなタイプのものでは全然ないのだから。ウォルドロンの音楽――最も抒情的な時にも獰猛で、最も軽快にスイングする時ですら何かしら陰鬱な――は、ウォーレン・ミラー原作小説の若者目線の語りからは感情的にずい分とかけ離れており、意図的にクラークが課した大人の同情的な視点という方法論の一端を担っている」。
マル・ウォルドロン・ウィズ・エリック・ドルフィー「ザ・クエスト」
「ビリー・ホリデイの最後の伴奏者であり、またプレスティッジ・レコードのハウス・ピアニストとして50年代後半に多くの録音を残したウォルドロンは同時にチャールズ・ミンガスのジャズ・ワークショップにおける古株にしてエリック・ドルフィーの相棒、頻繁な協力者でもあった。生来の実験精神の持ち主である彼は、既に評価は確立された身でありつつ、この時代のアヴァンギャルド・ジャズの目指すところに極めて共感を寄せるミュージシャンでもあったのだ。60年代前半の最良の仕事「ザ・クエスト」“The Quest”(Prestige)はハードバップといわゆるフリー・ジャズの連結である」。
ここに引かれたアルバム「ザ・クエスト」はマルとエリック・ドルフィーの創造的なコラボレーションが初めて記録されたセッションとして知られるものだ。特に有名な一曲が「ファイアー・ワルツ」“Fire Waltz”。録音は61年6月27日。この三週間後にジャズ・クラブ、ファイヴ・スポットで行われることになるライヴ録音で再び顔を合わせた二人は、再度このナンバーを共演し、決定的な名盤とした。そちらの模様は二枚のアルバム「エリック・ドルフィー・アット・ザ・ファイヴ・スポット1、2」“Eric Dolphy at the Five Spot vol.1 vol.2”(PRESTIGE)に収録されている(問題の「ファイアー・ワルツ」は第一集)。
ライナー紹介を続けよう。生前のウォルドロンは電話でインタビューに応じて、この企画に関わったのがカール・リーとの親交故であったと語る。リーは彼のためにディジー・ガレスピーを含む「ドリーム・バンド」を集めてくれた、とも。この時点でジャズを有効に使用した映画音楽は既に幾つも存在したが、ウォルドロンがスコア制作の参考にしたのはマイルス・デイヴィス音楽の『死刑台のエレベーター』“Ascenseur Pour l'Echafaud”とアート・ブレイキーとザ・ジャズ・メッセンジャーズ及びセロニアス・モンク音楽の『危険な関係』“Les Liaisons Dangereuses”の二本だけだった。そこで最も厄介だったのは場面につける音楽の長さだったという。「曲を書き、実際に演奏してそれがほんのちょっと(場面より)長すぎても、まさにそれは『長すぎるじゃないか』ということになる」。
そうした映画音楽固有の問題を気にすることなく、このオリジナル・スコア・アルバムでガレスピーは自身のバンドを率い、スタジオ入りすることが出来た。場面に合わせ圧縮されてしまった音源でなく、より自由に演奏出来たわけだ。
「ウォルドロンによる音楽はハ調の中央部周辺の音群で概ね書かれており、そのため密集し、窮屈な感じで必然固着した印象から逃れ難いものだった。ウォルドロンが演奏するとテンションとそこからの解放というやり方になりがちで、時にテンションだけで演奏されることにもなった。そうしたウォルドロンと威勢のいいガレスピー(既にヴァーヴにアルバムを残しそれらはうまくいっていた)の組み合わせは何とも奇妙なものと映ったはずだが、ガレスピーはそんなウォルドロンの音楽に彼自身のスタンプを押すのに成功している」。
ライナーはさらに詳細に楽曲の分析を行っている。
「紛れもなくウォルドロンのものとわかる不吉さをたたえた、セロニアス・モンク風のベース持続音も特徴的な『ストリート・ミュージック』やミンガスっぽいスイングが聴かれる『クーリー』がある一方で、『エンター・プリースト』のバップ的曲調はウォルドロンよりもガレスピーに結び付けられるべきものだし、その軽快な歩調はジョン・ルイスの『ゴールデン・ストライカー』を思い出させ、アルバム一番のキャッチーなナンバーになった。このアルバムがCDで再発されることをジェームズ・ムーディーとケニー・バロンに電話で知らせた際、彼らが喜んでスキャットしたのがこの曲だった。とはいえガレスピーの、曲がりくねってひしゃげた音色が雄弁な『ボニーズ・ブルース』では(映画においてはプリーストとその金髪のいかした恋人とが酔っ払って泣きながら歌うデュエットだったのが)、ガレスピーがウォルドロンの曲を演奏することで見つけた刺激がいかなるものであったかを最も納得させるに足る証拠になっている。この時代ガレスピーはマイルス・デイヴィスの影に隠れた存在となっていた、それというのもマイルスはより革新的なバンドを絶えず招集していたわけで無理からぬことではあるのだが、しかしこのCDで聴かれるガレスピーのクインテットは同時代の最も優秀なバンドの一つである。リーダー同様メンバー各自の音楽性や個性がにじみ、とりわけ、ムーディーがその頃(サックスの音色に)合体させようとし始めていた人間の声のような効果(例えば『デューク・オン・ザ・ラン』での咽喉をつまらせるような)、これはガレスピーのしゃべるような音色やバロンの早いテンポのソロと同じ意図から発されたものであり、二十歳になったばかりだったムーディーがいかに洗練された即興演奏家であったかを例証するものである。ルディー・コリンズは『クーリー』をピリッとしたリムショット(シンバルの縁を打つ手法)で活気づけ、『コニー・アイランド』ではクリス・ホワイトと共にビートの配分をきっちり同調させない刺激的なリズム・セクションの妙を供してくれる。この曲は、ウォルドロンの音楽へのベーシストの熱狂と深い洞察力が目に見えて明らかなものの一つと言える」。