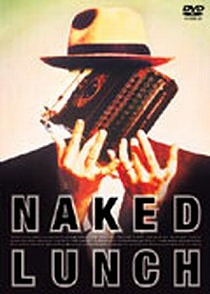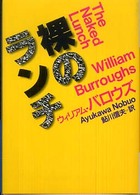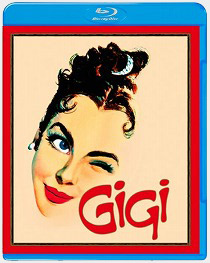映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第33回 アンドレ・プレヴィンのジャズ体験 その8 西海岸派ジャズマンとしての勲章
第33回 アンドレ・プレヴィンのジャズ体験 その8 西海岸派ジャズマンとしての勲章
映画とビート・ジェネレーション
ジャック・ケルーアックJack Kerouac(変った名前だがフランス系カナダ人の出自だから。故に、本名は正確にはeの上にチョンとアクセント記号みたいなのがつく)の小説に基づき、映画はフリードによって「ビート・ジェネレーション」を正当化すべく意図されたのだが、結果はふかふかの白パン「ワンダーブレッド」(白人を意味する俗語。上島注)の如きものとなり果てた。映画史家レナード・マーティンによる一言である。そして「MGMはこの映画のための撮影所じゃなかった」と。フリードの遺産と呼ぶに相応しく、『地下街の住人』は――ミュージカル映画ではないのだが――音楽映画を志向するもので、ビート・ジェネレーションの動きの中核であったジャズ美学を摑まえようと模索されていた。率いるのはMGMの天才児作曲家指揮者ピアニストのアンドレ・プレヴィンであり、この映画はウェスト・コースト派ジャズメンのオールスターを勢ぞろいさせた点で歴史的価値を持つものだ。ジェリー・マリガン、カーメン・マクレー、シェリー・マン、レッド・ミッチェル、バディー・クラーク、デイヴ・ベイリー、アート・ペッパー、ラス・フリーマン、ビル・パーキンス、ボブ・エネヴォルドセン、ジャック・シェルドン。映画自体は様々なイデオロギーの集中砲火にさらされて突然変異を遂げてしまったとはいえ、プレヴィンの音楽は純粋で、ジャズを使った映画音楽のサントラとして最も良質なものの一つであり続けるに違いない。
原作小説は1953年の10月(ベンゼドリン漬けの72時間のさ中において)書かれたが、出版されたのは1958年だった。多くのケルーアックの小説同様これは「意識の流れ」を記述する文体で構成されており、半自伝である。1953年八月に著者と人種混交女性との間に起きた恋愛沙汰を綴ったもので、ニューヨークのボヘミアン芸術家、慣習に囚われない「はみ出し人」達を背景にしている。ただし小説化に際し、舞台をサンフランシスコに変えてある。ケルーアック(1922-1969)は第二次大戦後物書きとなり、アレン・ギンズバーグAllen Ginsberg、ウィリアム・S・バロウズWilliam S. Burroughs、ルシアン・カー、ニール・キャサディー達、作家で友人でもある人々と共に「ビート」の運動を創始した。実のところこの言葉を創り出したのが彼である(後述)。
1950年代晩期、作詞家出身のプロデューサー、アーサー・フリードに、そのキャリアの終りの時が近づいていた。フリードのキャリアとは、かつて作られた最も偉大なるミュージカル映画のプロデューサーたることであり、ほんの二三名前を挙げるなら『パリのアメリカ人』“An American in Paris”(監督ヴィンセント・ミネリ、51)『雨に唄えば』“Singin’ in the Rain”(監督スタンリー・ドーネンとジーン・ケリー、52)『恋の手ほどき』“Gigi”(監督ミネリ、58)等である。フリードは、原作がベストセラーとなっていたにも関わらずわずか一万五千ドルで映画化権を獲得。彼はこの映画を、その頃都市部に出現した進歩的なジャズを大いに楽しみ、人種差別撤廃を心から望む若者たちの意気に忠実たらんと意図していた――だが、これでは予算をかけた娯楽映画には不向きで、儲かりそうもない。フリードは映画を、きらびやかなMGM色を取り去った低予算の白黒映画にするのが最善と考えた。フリードの力をもってすれば出来ないことではなかったが、多分そうした影響力を行使してまで長年の雇用主達と闘うには彼はもう疲れ果てていたのだろう。最初にやったことは――当然だが――チェロキー先住民と黒人とのハーフだった恋人役を白人フランス女性に改変すること。そして映画はシネマスコープのメトロカラーで撮影されることが決定――質素さの美学には(製作費が)高価すぎる。脚本家ロバート・ソムは原作からはわずか三人の主要人物しか残さなかった。
フリードとソムは共同製作者を兼ねる監督に若い才能を望み、当初デニスとテリーのサンダース兄弟を起用したが結局二週間しかもたず、ラナルド・マクドゥーガルに替わった。兄弟は、挑発的な主題を骨抜きにするのに失敗したせいでクビになったのだと主張したが、フリードはそういうわけではない、と静かに取材陣に語るのみであった。新しい監督は脚本も書き直し、リアリズムで押し、主演俳優同士の反感をうまいこと利用しさえした。ロケ撮影もあっという間にこなし、「これこそまさにMGMだぜ!」“It’s too Metro”が彼とスタッフ、キャストの合言葉となった。みんな御機嫌だったが、残念ながらMGMだけはそうでもなかったのだ。ヒュー・フォーディンHugh Fordinによるフリード伝「娯楽の世界」“The World of Entertainment”には以下のような記述がある。
1960年1月20日、エンシノ劇場で映画は試写されたものの、場内に灯りが点いたとき撮影所関係者はあ然として声も出なかった。どうしたらいいのか誰にもわからなかったのだ。映画は新しいタイプの若者たちのフラストレーションや混乱、困惑を提示したものだ。開かれた心を持った者ならば誰もが、本当は傷つきやすい繊細な心を持った若者たちを非難するというより、一体何が彼らを孤立させ、何が彼らの行動を動機づけているのかを理解しただろう。ところが映画『地下街の人々』はバラバラで到底理解不能な代物であった。検閲上は何の問題もなかったにも関わらず、MGM編集部責任編集者で女性スタッフ陣の最長老マーガレット・ブースは意味不明なまでに映画を切り刻んだ、それというのも「アメリカ的価値観」を擁護し、レオ(MGMのシンボル。会社ロゴの白いライオンのこと)に健全な一吠えを保護する努力故である。
(映画本来の主義主張とは)全く両立するはずのない主義主張を満足させるために骨抜きにされ、完成した作品は誰をも納得させなかった。「これを現実というには大ざっぱに過ぎ、風刺と呼ぶにはわかりにくい」とハリウッド・レポーター誌。
当時の代表的な反応を掲げておく。ニューズウィーク誌、「ビート族が本当に反抗的グループならば、このカラー映画は彼らに、抗議するに足る確固たる理由を与えている」。フィルムズ・イン・レビュー誌、「サンフランシスコのビート族に関するジャック・ケルーアックの小説の映画化権を買ってしまったのが最初の過ち。こうした荒廃した人心を描写することは今日の映画にあってもあまりに嫌悪を催すものだ」。サタデー・レビュー誌は何の役にも立たない提案をしている。「この見込みのない企画には、コムデン&グリーン・コンビやジュール・スタインが絶対に必要であった。アーサー・フリード氏に彼らを雇う深慮遠謀があったなら、今年度のベスト・ミュージカル映画間違いなしだったのに」。これだけ読むと冗談か本気かよくわからない文面だが。そういうわけで『地下街の住人』はほとんど忘れられてしまった。「凡人(スクエア)」がいかにどうしようもない間違いをしでかすか、これを見て笑い物にするというのが今日、映画ファンをして鑑賞の主たる目的となっている。ただし凡人でないのがただ一人。我らがヒーロー、アンドレ・プレヴィンである。