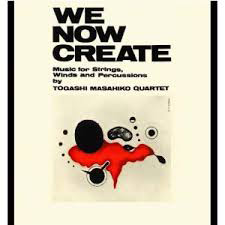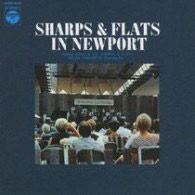映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第68回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼その6
第68回 人間国宝ジャズ 山本邦山追悼その6
パーカッショニスト富樫雅彦
同じく「パラジウム」より富樫のプロフィールを引用する。本アルバムでは、ドラマー、パーカッショニストとして、富樫雅彦が重要な役割を果たしている。(略)1940年の東京生まれ。音楽家の父親に影響され、幼少から音楽に興味を持ち、中学生になると、ジャズに関心を持ち、14歳で、プロのドラマーになった。渡辺貞夫カルテット、佐藤允彦トリオ、高柳昌行との双頭グループなど、常に日本の中心的プレイヤーと共演を行い、創造的なドラマーとして注目されてきた。ただテクニックのあるドラマーにとどまらず、人間の心や精神をドラムスという楽器を通して表現し、聴く者の心をゆさぶってきた。69年には事故で、車椅子生活を余儀なくされたが、彼のドラミングはさらに深化していった。独自のドラム・セットも考案し、パーカッショニストとして、広大な世界を創造し、深くて高い精神の表現を追求してきた。
富樫にとって、この録音時点は事故の前であることを特記しておく。「ジャズ批評」誌53号「これがジャズ・ピアノだ」では、佐藤がインタビューに応えて「パラジウム」を語っている。
僕にフリーのおもしろさを教えてくれたのは富樫さんですね。バークリーから帰ってきたのが六八年で、その年の暮れから彼とトリオを組んだんだけれど、ことあるごとに「フリーやろうよ」なんて言う。それで、「いいよ」なんて調子で始めたわけです。(略)「ミシェル」について言えば、結局あれは論理的な演奏なのね。こうしようと思っていて、その通りになって行く。富樫さんはそういうのがイヤだったんですね。ビートたたくだけだったら、いくらでもいいのがいるから、俺たちはそうじゃないとこ行っちゃおうなんて。ビートよりもっとトータルなパルスということを、彼は当時すでに考えていましたね。
宮沢昭「フォー・ユニッツ」
宮沢昭「いわな」
鈴木弘&富樫雅彦「ヴァリエーション」
高柳昌行&富樫雅彦「ウイ・ナウ・クリエイト」
「ビートよりもっとトータルなパルスを」という宣言にも含蓄がある。パルスとは要するにリズムの自発的な脈動、自在なうねりという意味だろう。ピアノ、ベース、ドラムス(パーカッション)という三者が演奏を繰り広げるという時に、ベースとドラムスがフォービートを底部でがちっとキープしてピアニストのソロをスイングさせる、という従来的方法に留まらず、三者それぞれのアドリブを展開しやすくするために、トリオの音楽的底部(ビートのキープ)という概念を外す、というアイデアがそこに読みとれるからだ。
実は「パラジウム」に先駆けて、このトリオは確認出来る限り二枚の別アルバムに録音参加している。どちらもリーダーはサックス、フルート奏者宮沢昭でアルバムは「フォー・ユニッツ」“Four Units”(テイチク・ユニオン)と「いわな」“Bull Trout”(ビクター)である。宮沢がトリオに惚れこんでレコーディングでの共演を切望したのだと「いわな」ライナーノーツで油井正一が述べている。つまりメンバー構成としてはレギュラー・ピアノ・トリオにゲスト的に管楽器が加わるもので、また宮沢が佐藤の一世代上(つまり富樫の同世代)のミュージシャンということもあって、明らかに「パラジウム」よりも以前のジャズである。アルバム「いわな」の、タイトル曲とラスト「虹ます」を聴き比べればそれがよく分かる。前者が「宮沢」としてはよりフリー・ミュージック寄りで、後者がハードバップ寄りなのだ。トリオの斬新な方法論にインスパイアされて宮沢が前者にチャレンジする一方で、従来のやり方の後者も録音したということになろう。
前者は30分近い長さ。個々の局面でフリーに流れる傾向と全体的に極めて構築的な演奏とが混然一体となった好演である。しかも途中で全員がパーカッションを演奏するパートが用意されているのが面白い。もちろん宮沢が最初から考えて行ったのだが、どこかしら「フリー・ジャズにおけるパーカッションの優位性」みたいなものを感じさせないではいない。そして後者では四者のスマートな一体感は当然として、さらに管楽器が抜けて通常のピアノ・トリオになった場面で「パラジウム」にはない「フリー以前のモダン・ジャズ」の醍醐味が味わえるのだ。これまた面白い。例えて言えば「ナウ・ヒー・シングス・ナウ・ヒー・ソブス」“Now He Sings, Now He Sobs”(SOLID STATE, BLUE NOTE)のチック・コリア・トリオ(ベースはミロスラフ・ヴィトウス。ドラムスはロイ・ヘインズ)のような。これはコリアの方法に佐藤が追従するのではなく、両者のピアノ奏法の同時代性を示すものと分かる。ヴィトウスと荒川康男も全く同時期にバークリーに学んだ仲なので、ベース奏法の同時代性ということもあるかもしれない。
この69年、佐藤允彦トリオに参加する(「パラジウム」以外にも作品はあるが今回は省略)のと並行して富樫は富樫で別なユニットを幾つか作り、初めてのリーダー・アルバムも発表している。1、2月録音の「ヴァリエーション」“Variation”(タクト、日本コロムビア)がそれでトロンボーンの鈴木弘との双頭リーダー作。5月録音の「ウイ・ナウ・クリエイト」“We Now Create”(ビクター)はギタリスト高柳昌行との双頭リーダー作。さらにサックスの高木元輝を起用した「スピード・アンド・スペイス」“Speed & Space”(テイチク・ユニオン)もある。この作品についてはいずれ映画『略称・連続射殺魔』(監督 足立正生、69)と一緒に取り上げるので今回は省く。前者「ヴァリエーション」は多分鈴木の趣味でクロスオーヴァーというかイージー・リスニング・ジャズの血液が流れ込んでいて、それが当時は評価を落とさせる要因になっていたはずだが、今聴くとかえって興味深い。例えば、普通ジャズの世界で「アルフィー」“Alfee”と言えば同題映画(監督 ルイス・ギルバート、66)で使われたソニー・ロリンズ作曲のアップテンポなテーマ楽曲を指すものだが、ここではポップス畑のバート・バカラック作曲による主題歌の方をわざわざジャズ化している。フリーに限りなく傾斜した「鈴の唄」と続けて聴くと実に不可思議な感触だ。これについては、いかにも「時代の音楽」としていずれまた触れる機会もあろうが、今回は「ウイ・ナウ・クリエイト」のライナーを紹介しておきたい。
このアルバムは「パラジウム」と一緒にスイングジャーナル・ジャズ・ディスク大賞の「日本ジャズ賞」を受賞しており、要するに富樫はダブル受賞である。別に賞を取ったから偉いとかそういうことを言いたいわけではないが、ジャズマンとしての評価のトップに立ったとは言える。「ジャズ空間」と題されたライナーは富樫の自筆である。全文引用するには長いのではしょりながら紹介したい。
私の周囲には、さまざまな形でリズムが存在している。(略)雨の日に耳をすましてみる。そこには、きたない音、きれいな音、(略)力強い音や弱々しい音等がある。(略)これらの中から、私は“リズム”を感じ、さまざまな“響き”を感じつつ、そして“空間”を感じはじめる。(略)絵画は現実の時間をもたないから、画面の内部に永遠の時間を表現しようとする。同じように、私はジャズの内部に空間を探し求める。リズムの流れの中に空間を創り出すのだ。(略)音と音の重なり、それがリズムの流れの中で多様な交錯をする。(略)それは、従来言われている曲構成とは次元を違えたものである。空間の中には、現実に進行しているリズムともテンポともビートとも違った、もう一つのリズムが出来上がる。(略)それは私自身の宇宙空間の中の、永遠のリズムである。四部構成をもった、このアルバムの中で、パートからパートに移る沈黙の部分にも空間としての音楽は存在しているし、さらに言えば、このアルバム全体が、私達の永遠のリズムの中での1拍であると思っていただきたい。
富樫がここで述べようとしているのは、彼が目指す「黒人音楽としてのジャズではないジャズ」の起点に「黒人的じゃないリズム」を据えてみようという提言である。単純すぎる言い換えではあるが「フォービートじゃなく永遠のリズムを」とすれば分かりやすいだろう。そして富樫にとって「永遠のリズム」とは「沈黙」の音楽的活用、要するに日本的、東洋的な「間(ま)」なのである。これが、前回のテーマの一つである「山本邦山の空間音楽の規定」に連携するものであるのは言うまでもあるまい。
演奏者自身による、いわば「ジャズ空間」宣言を受け、80年の再リリース時に改めてつけられた野口久光のライナーではアルバムをこう総括している。「富樫は1960年後期において、70年代以降の飛躍への第一歩を踏み出しており、ジャズの伝統的なセオリー、精神を踏まえた上で、まったく常識的なジャズの形式や奏法を超えたユニークな音楽志向を、作曲と演奏に結実させているのである。(略)これこそ日本のニュー・ジャズといえる音楽というべきものであろう。」この「日本のニュー・ジャズ」という言葉は、かつて山本邦山が原信夫とシャープス・アンド・フラッツと共演した際(「ニュー・ジャズ・イン・ジャパン」“New Jazz in Japan”「ニューポートのシャープス・アンド・フラッツ」“Sharps and Flats in New Port”《共に日本コロンビア》等)にキャッチフレーズとしてもたらされたものであったのを思い出してもらいたい。
とはいえ、音楽的な共通点をそこに見出すのに大して意味があるとも思えない。要するに60年代終わりに、日本のジャズの色々な場面で日本的なオリジナリティを人々は要求するようになったのだ。正確には、この時点で突然にそれが求められたのではなく、ずっと以前から求められていたのだがそれへの幾つかの解答が認められるようになったのだ、と言うべきか。バンドリーダー原信夫とアレンジャー前田憲男にとっては、山本邦山の尺八をフィーチャーした日本的旋律のジャズ化がそれであり、パーカッショニスト富樫雅彦にとっては日本的な「間」のジャズ的活用を指す。片や旋律で、片やリズムで日本がクローズアップされるように見えるが、それを少し保留したいと思う。70年代初頭に執筆された油井正一「ジャズの歴史物語」にはラスト部分に、都市黒人娯楽音楽としてのジャズという視点をいったん解体して、より広い時間空間にこの音楽を置いてみるとどんなことが見えてくるか、という極めて刺激的な記述が読まれる。即ち「民族音楽としてのジャズ」。その結論部を引用する。ちょっと長いのだが私が「日本を保留する」とした意味が読めるはずだ。
ジャズは民族音楽として生まれ、民族音楽として成長した。もはやアメリカだけの黒人音楽といったせまい視野から眺めることは許されない。アフリカはむろん、中近東、印度あるいは日本にもルートのある民族音楽かもしれないのである。シャープス・アンド・フラッツが尺八の山本邦山とニューポートに出演して、日本民謡をジャズったとき、誰も笑わなかった。かわって熱烈な拍手を送り、全批評家が絶賛した。(略)十五年前だったら一笑に附されたかもしれない。(略)これが一九六〇年代のジャズ批評の新傾向なのである。つまりジャズは意外に根の深い民族音楽であり、民族音楽の歴史には非常な交流が行われてきたことがわかったのである。それをわからせたのは「先祖がえり」を示したジャズメンの勇気と率直さであった。
油井が最後に記した「先祖がえり」とは、アメリカのフリー・ジャズの面々が自らの音楽にアフリカ的要素、中近東的要素を積極的に取り込むようになった、当時十年ほどの傾向を指す。だから「先祖」といっても近いご先祖ニューオリンズではなく、そのさらなる起源へと時間空間をさかのぼる運動である。これは富樫が「フォービートじゃなくパルスを。永遠のリズムを」と訴えたのと軌をいつにしているではないか。例えば、タイトルもずばり「永遠のリズム」“Eternal Rhythm”(MPS)というアルバムをフリー・ジャズ系トランペッター、ドン・チェリーが68年にリリースしている。「ウイ・ナウ・クリエイト」はこのアルバムと直接の関係はないし、両者の人脈的関連もないが、富樫もこの言葉自体は知っていたかもしれないし、或いはここから取った可能性もある。
チェリーは、この作品ではバリ島のガムラン音楽にヒントを得て楽想を展開するのだが、決してインドネシアの民族音楽のコピーではない。また厳密には民族音楽とジャズの融合とも言えないだろう。そうした視点で見れば、ガムランの使用法は伝統音楽に根ざしたものではなく単に楽器として扱われているだけだからだ。本盤で目指されているのは、メロディーで区切られる単位としての楽曲の展開でなしに、リズムの氾濫によって単位を解消しようとする運動である。レコードのAB面でかろうじて裏表は区切られるものの。チェリーが言う「永遠のリズム」とはそういう含意だと考えられる。富樫の言う「永遠のリズム」とそれが同じものだとする必要はないし、むしろ言葉が「同じ」だけに概念自体は「異なる」としておきたいが、とりあえず何か共通する気配はある。そして現にチェリーと富樫は74年、チェリー来日時に知己となり、79年にはベーシスト、チャーリー・ヘイデンを加えてアルバム「富樫雅彦セッション・イン・パリ,Vol.1」“Masahiko Togashi Session in Paris Vol.1”を一緒に作ることになるのである。
山本邦山が佐藤允彦に誘われてフリー・ミュージック系の即興演奏を行っていた時、そのコンボのドラマーは果たして富樫雅彦だったのだろうか。残念ながら音源が発表されていない(録音もされなかったのだろう)から、何とも言えないがそれが70年1月中旬以降ならば、富樫はセッションに加われなかったはずだ。この1月、富樫は不慮の事故で下半身の自由を永久に奪われることになるのである。(続く)