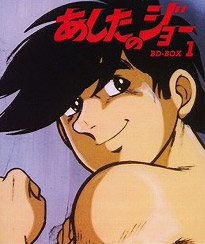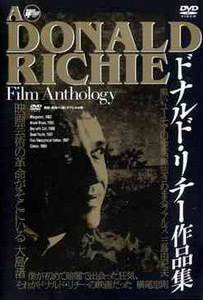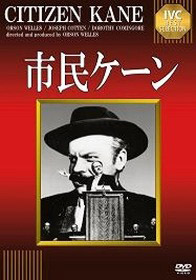映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第51回 60年代日本映画からジャズを聴く その9 セロニアス・モンクの衝撃と「喧嘩セッション」
第51回 60年代日本映画からジャズを聴く その9 セロニアス・モンクの衝撃と「喧嘩セッション」
映画作家ドナルド・リチーと八木正生の接点
オラシオさんのリスニング・イヴェントに関連づけて三回にわたりポーランド映画とジャズとクシシュトフ・コメダを語ってきた。彼のブログ「オラシオ主催万国音楽博覧会」ではコメダ・グループ・メンバーだったトマシュ・スタンコの最新アルバムの話題が「熱く」語られていて真に頼もしい。ポーランド・ジャズにおいてコメダという存在はいわば「共通分母」の一つなのだ。こちらの短期連載ではとうてい語りきることのかなわないテーマである。いずれまたとり上げるつもりだが、とりあえず八木正生と日本映画に戻ろうと思う。オラシオさんのツイッターを読むと今回のテーマにかする「モンク曲集」の最新の一枚のタイトルも挙げられていて、シンクロニシティみたいな現象が起きている。
「ドナルド・リチー作品集」
それにしてもこの話題を開始したのはもう一年も前のこと。月日の経つのは早い。
この2月19日。日本映画の研究家として知られるドナルド・リチー氏が亡くなった。1924年生まれの88歳。ご冥福をお祈りします。氏の仕事で最もよく知られるのは著書「黒沢明の映画」(三木宮彦訳、キネマ旬報社、他、刊)と「小津安二郎の美学 映画の中の日本」(山本喜久男訳、フィルムアート社刊)だろう。彼のキャリアをくまなく紹介するのは私の任ではない。それと「高崎俊夫の映画アットランダム ドナルド・リチーのアンダーグラウンドな戦後史」が、短いけれども少し異なる視点からその仕事の思いがけない広がりを論じている。
だが今回この連載で急いで記述する必要があるのは映画史家でなく映画作家としてのリチーである。DVD「ドナルド・リチー作品集」“A Donald Richie Film Anthology”(ダゲレオ出版刊)も2001年にリリースされ、それに合わせて映画回顧展(2001年3月17日~4月6日)も開催された。「反逆とユーモアの詩的映画の世界」と題されたインタビューを、この企画のWEBで現在でも読むことが出来る。『市民ケーン』“Citizen Kane”(監督オーソン・ウェルズ、41)で映画に目覚めたという氏が8ミリカメラを回し始めたのはまだ十代の1941年だというから、そのフィルモグラフィも意外と広範にわたるのだが、DVDに収められたのは60年代製作の5本のみ。タイトルは『戦争ごっこ』(62)『熱海ブルース』(62)『猫と少年』(62)『死んだ少年』(66)『五つの哲学的童話』(67)『シベール』(68)である。 何故ここで彼の作品歴を挙げたかというと注目は『熱海ブルース』“Atami Blues”にある。連載第47回の最後に記したように、この武満音楽による短編映画でセロニアス・モンク風のピアノを弾いていたのが八木正生だと思われるからだ。