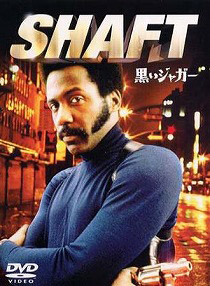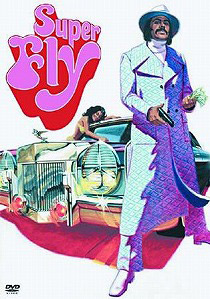映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第34回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その1 映画『ザ・コネクション』を巡るコネクション
第34回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その1 映画『ザ・コネクション』を巡るコネクション
ザ「コネクション」コネクションズ
映画『ザ・コネクション』は「ジャンキー映画」の先駆けとしてそれなりに有名になった。我々が現在見られるのはこの映像であり、舞台の方は、21世紀の再演版を見られた原田氏のような方を除けば日本人で見ている人を知らない。一応確認しておくが、この映画は舞台を収録したものではなく、また実際の集合住宅を使って安く上げたものでもなく、きちんとプロの映画美術家を起用してセットを建て、映画のキャメラマンが撮影したものである。だから舞台オリジナルそのものの演出や趣向は映画を見てもあまりよくわからない。むしろ極めてまともな劇映画である。一方、舞台は舞台で映画版とは異なる展開を幾つか見せた。なにしろ舞台は生ものだから、とにかく決まった上演予定時間にそこに俳優がいないといけない。当然だが。また細かい手直しも随時行われるものだ。こうした、映画と異なるメディア上の要請により本作の舞台も初演当時の数年間で様々なバージョンを持つ。それに応じて音楽も少し変る。それらの変異全てを私が把握しているわけではないが、それでも私がわかっている限りでの違いを記しておきたい。
ずフレディ・レッド率いる四重奏団のパーソネル(既述)は舞台用に選ばれたメンバー。ジャッキー・マクリーンの起用は、彼がチャーリー・パーカー系のアルト・サックス奏者だったことによる。レッドに依頼する以前から作者ゲルバーは舞台に登場するジャズマンを「パーカー系サックス奏者」と規定していたからだ。ベース、ドラムスが当初固定されなかったことは既に記した。マクリーンが都合のつかない日はティナ・ブルックスが代演したと言われる。彼はアルトでなくテナー・サックス奏者だがこの場合にはアルトを吹いていたと思われる。ブルックスは自作「シェイズ・オブ・レッド」でマクリーンと共演。これも既述。
面白いのは60年6月13日に録音されたセッションの存在で、そこからキャストの変遷も読める。これは「ミュージック・フロム・ザ・コネクション」“Music from the Connection”(Iris Records)のタイトルでリリースされた。セッション・リーダーはハワード・マギー(トランペット)だが、ブルックスもちゃんとここにはアルトで参加してブルーノート版「コネクション」と全く同じ曲を同じ順に演奏している。原盤ではピアニストがI・チンの名前になっているが、これが実はフレディ・レッドの変名であったことも現在では判明している。
どういう事情でこのアルバムが作られたのかはわからない。重要と供給の関係で言えば、ブルーノートは弱小レーベルで最初のリリース枚数も少ない目だったことは間違いない。レコードを置いているショップもメジャー・レーベルに比べれば限られていただろうが、だからと言ってわざわざ他のレーベルからほとんど同じタイトルのアルバムを出すような根拠になるのかどうか。こちらもまたマイナー・レーベル作品だし。
マギーが積極的にやりたかったのかプロデューサー主導か、あるいはやっぱりレッドがリーダーだったのか、これも全然わからない。日本盤CDのライナーを書いた上條直之によると、他のメンバーはともかくマギーのトランペットはちょっとショボいのではないかとのこと。やはりマギーはダシにされただけだったのかも。いずれにせよブルックスの舞台演奏を想像させる点で貴重な盤になっている。
この盤の存在は日本でも早くから知られていたが、近年もっと変ったアルバムがアメリカで発売された。タイトルは「ミュージック・フロム・ザ・オフブロードウェイ・プレイ・ザ・コネクション」“Music from the Off-Broadway Play the Connection”(Fresh Sound)。全14曲が収録されており、前半七曲は参加メンバーから考えてハワード・マギー版「コネクション」だと思われる(録音年月日が違うけれども多分同じもの)。問題は後半七曲の存在。これの作曲者はセシル・ペイン(バリトン・サックス)とケニー・ドリュー(ピアノ)となっているのだ。パーソネルを一応紹介するとペイン以外にクラーク・テリー(トランペット)、ベニー・グリーン(トロンボーン)、デューク・ジョーダン(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)、チャーリー・パーシップ(ドラムス)。つまり作曲の一人ドリューは参加していない。これはどういうことなのか。ここでも「ザ・ブルーノート ジャケ裏の真実」が参考になる。「『ザ・コネクション』は60年11月までのロングランとなり、この間に映画化もされる大成功を収めた。61年前半にはヨーロッパ・ツアーも敢行されたが、皮肉なことにレッドは麻薬で体調を崩し、ツアー直前になって参加をキャンセル。そこで前半をケニー・ドリュー、後半をデューク・ジョーダンが務め、急場をしのいだのだった」。
ライナーを執筆したのはアイラ・ギトラー。レコードの発売日は正確にはわからないが、録音が61年5月6日だから、西海岸版の舞台が欧州公演に先立ちニューヨーク公演の後だったことは確定出来る。ティナ・ブルックスとは異なり、ゴードンは自分をリーダーにしたカルテットで新たに西海岸版のために音楽も作曲したものであろう。ゴードンもまた有名なジャンキー・ジャズマンで五十年代のほとんどを麻薬療養のために棒に振っている。彼についてはいずれ別稿で語りたいところだ。
アルバム「コネクション」を巡るコネクションはこれでは終わらない。さらにヘンなアルバムも生まれている。ジョニー・グリフィス(ピアノ)の「ジェネヴァ・コネクション」“The Geneva Connection”(GeNeva Records)である。録音データは74年1月6日、9日。ライナーはまたも原田和典でさっそく引用する。
「当アルバムの大きな魅力はグリフィスがモダン・ジャズ史上に残る名曲集『コネクション』をまるごとカヴァーしていること、これに尽きる。もっと噛み砕いて言えば、モータウン・レーベルきっての職人ミュージシャンであるグリフィスが、ジャズ界最強といわれるブルーノート・レーベルのハード・バップ名盤に収められていたナンバーを取り上げ、しかも全く新しいアレンジでジャズ・ファンクの逸品として生まれ変らせているのだ」。
本稿のテーマから離れ過ぎるのでグリフィスについては触れない。ただ原田が推測しているように、突然「コネクション」カヴァー盤が現れたのは70年代初頭の「ブラクスプロイテーション」(黒人娯楽映画)ブームが関係しているのだろう。『黒いジャガー』“Shaft”のアイザック・ヘイズと『スーパーフライ』“Superfly”のカーティス・メイフィールド、この二人による映画音楽自体が映画をはるかに凌駕する評判を呼んだことで、70年代以降、映画と映画音楽の関係ががらっと変る。大ざっぱに言えば黒人映画よりも黒人音楽の方が人々にとって大きな存在となる。そうした流れの一端にこのファンク「コネクション」が位置しているわけだ。ピアニストのグリフィスをリーダーにしたセッションではあるが本盤の音楽監督はフロイド・ジョーンズ(トランペット)で、制作はジョーンズとこのレーベルの監修者アーネスト・ケリーの二人。実は、ケリーはマギー盤「コネクション」のプロデューサーでもあったのだ。やはりマギーは西洋ダシ(ブイヨン)で、レッドの舞台音楽に惚れ込んだのがケリーだったということかも知れない。