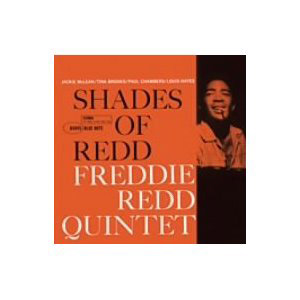映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第34回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その1 映画『ザ・コネクション』を巡るコネクション
第34回 アメリカ60年代インディペンデント映画とジャズ その1 映画『ザ・コネクション』を巡るコネクション
ピアニスト兼音楽監督フレディ・レッド
そろそろレコード・アルバム「ザ・ミュージック・フロム・ザ・コネクション」(以下略して「コネクション」とする)の話題に移りたい。このアルバムは映画のサントラ盤だと考えられている。私自身は映画とアルバムを厳密に比較したことがないのだが、そうであっておかしくないからそうだろうと思う。気になるのは映画のリリース年は62年なのに録音日が60年2月とずい分離れていること。ただし、やはり単にブルーノートの主宰者アルフレッド・ライオンが舞台音楽を気に入ったためにアルバムを作ったのではない証拠がジャケットに印刷された「W・ゼヴ・パッターマンとの共同制作」の文字であり、このパッターマンという人物が何者かは不明であるにしても、映画制作がらみのアルバムであろうとは推測されるのである。舞台では当初ドラマーとベーシストは固定していなかったそうだが、アルバムと映画でこの二人、ラリー・リッチー、マイケル・マトスが一致するのも状況証拠として十分だ。
この二人はほぼ無名のジャズメンで、そういう意味では録音も貴重。腕前だけでは録音機会にもそう簡単には恵まれないのが本場アメリカのジャズ・シーンである。アルト・サックス奏者は既述のジャッキー・マクリーン、音楽監督兼ピアニストはフレディ・レッド。マクリーンに関しては今回パスしてレッド中心に記述する。ブルーノートからリーダー・アルバムを発表してレーベルの目玉になっていたマクリーンがレッドをアルフレッド・ライオンに紹介したことでここでの録音セッションが実現したものである。もっとも、この件に関してはそれ以上の情報はない。映画のサントラ盤とはどこにも書かれていないのだ。舞台版制作のバックストーリーはライナーノーツに紹介されている。
「ゲルバーの紹介で(略)仕事を与えられたフレディは、舞台劇の音楽を書くのが長年の夢だったことを彼に伝える。(略)フレディは作曲に取りかかった。そしてゲルバーと相談しながら、音楽が入る箇所を正確に決めていく。フレディは筋書きをしっかり頭に入れ、各曲の雰囲気やテンポを細かく設定した」。こうして舞台用に書かれた七曲が映画にも流用されることになった。
「ジェリー・トルーマーは劇中のジャズを高く評価したほか『有機的かつダイナミックに』モダン・ジャズを取り入れた初めての劇作家としてゲルバーを讃え、ジャズが『さまざまな苦悩、均衡状態、常に存在する危機感などを支えながら、あるいはそれらに反発しながら、なんともスリリングな躍動感を生み出している』と評した」。
ピアニスト、フレディ・レッドとはどんな経歴の持ち主だったのだろうか。
それについてはこのブルーノート盤以前に録音されたフレディ・レッド・トリオ名義の「サンフランシスコ・スイート」“San Francisco Suite for Jazz Trio”(Riverside)の日本盤ライナーノーツ(これも小川隆夫執筆)を読めば良い。1928年5月29日ニューヨーク生まれのレッドがピアノを始めたのは十八歳の時、46年、チャーリー・パーカーをレコードで聴いてジャズを志した。徴兵されて韓国に行き、独学でめきめき腕を上げてアーミー・バンドで仕事を得るようになったというから、一種、天才肌の人物だ。除隊後ニューヨークでオスカー・ペティフォードのグループに抜擢されるのが49年。初のリーダー・セッションは55年でプレスティッジから。翌年スウェーデンに楽旅。帰国後サンフランシスコに腰を落ち着ける。しばらくこの地で活動し、ニューヨークに戻るとこのアルバムで聴かれるトリオを結成し、57年リヴァーサイドで本作を作る、という流れである。『ザ・コネクション』の仕事(舞台出演)が浮上するのがその二年後だが、準備段階から作者と協議を重ねていたとされるから、この頃からのつき合いに違いない。
そういう意味では本アルバムの目玉が「サンフランシスコ」をテーマにした五つの叙景的パートからなる十三分の組曲だというのも興味深い。『ザ・コネクション』の七曲が大ざっぱに言うと心象的なスケッチだったのに呼応するように見えるからだ。といってもことさら「叙景」と「心象」とを二分法的に裁断しているわけではなくて、要するにこうした極めて楽曲構成的な、つまり作曲家的なスタンスを業界の中で取っていたのがレッドであったと解釈出来るのだ。ジャズ・ピアニストという人種は例外なく作曲家的側面を持っている(そうでないとアドリブが出来ない)のだが、そういう個性を前面に打ち出すコンポーザー・タイプと解釈家(インタープリター)的態度に留まるタイプと二種類ある。レッドはまさに前者だったわけだ。
舞台ロングラン継続中の60年8月13日、レッドは引き続きブルーノートにリーダー・セッションを持つ機会に恵まれた。こうして発売されたアルバムが「シェイズ・オブ・レッド」“Shades of Redd”(Blue Note)である。このライナーもアイラ・ギトラーの担当で、当然ながら話題はこの舞台からだ。以下、小川隆夫の著書「ザ・ブルーノート ジャケ裏の真実」から引用。
「芝居『ザ・コネクション』の音楽を担当して注目を集めて以来、キャリアの割に不遇だったフレディ・レッドもやっと正当な評価を得つつある。彼は劇中で無口なピアニストの役を演じ、説得力ある演技を披露した。しかし再び舞台の仕事を望もうとも、フレディは本質的にジャズの作曲家にして演奏家であり、そして、このアルバムは彼がジャズ専門の元気な作曲家として成長した姿を示すものだ。(略)このアルバムの制作にあたり、フレディが細心の注意を払ったのは、作曲することと演奏することをいかに結びつけるかだった。出来映えは『ザ・コネクション』以来のいかなる経験と比べても、満足のいくものだったと彼は自負している」。
日本盤CDのライナーは原田和典が担当。ところがこちらにはこんな文面も見られる。「彼がBNに吹き込むようになったのもやはり『ザ・コネクション』がきっかけとなっている。舞台を見て感激した同レーベルの首脳陣、アルフレッド・ライオンとフランシス・ウルフがレッドに演劇の挿入曲をレコーディングする話を持ちかけたのだ」。
とりあえずこの説は「サントラ盤」説と符合しない。どうしたことだろう。原田がこの話をどこから引いてきたのかがよくわからないので、これ以上は何も書けない。ひょっとしたら原盤ライナーにそう記述されているのかも、と考えたが手元にそれがないのであった。残念。もっとも、大岡裁きをここに適用して両方丸く収めるならば、制作されたアルバムを映画に流用したとすれば良いわけだ。それならば映画のリリースと楽曲録音日が離れていることも合理的である。ともあれ「シェイズ・オブ・レッド」に話題を戻す。
挿入曲集の出来に大いに満足したBNは次作の件をレッドに打診する。今回も七曲全部レッドのオリジナル。作曲志向の強いレッドだから当然ではあるが、そもそもアルフレッド・ライオンという人がセッション・メンバーにオリジナル曲をどしどし書かせる稀有なプロデューサーだった、という僥倖もある。意欲を見せるレッドはサックス奏者を二人にした。前作のマクリーン(アルト・サックス)にテナーのティナ・ブルックスを加えるコンセプト。この楽器コンビネーションはレッドにも初体験でどうなるか不安だったらしいが、杞憂であった。またマクリーンとブルックスもウマが合い、ブルックスは自身のリーダー・アルバム「バック・トゥ・ザ・トラックス」“Back to the Tracks”(Blue Note)セッションにもマクリーンを招いている。「シェイズ・オブ・レッド」での原田お勧めナンバーは冒頭の「セスピアン(役者)」“Thespian”で、「三本目の管楽器のようにからむベースの弓弾きがハーモニーに重みを加え、テーマ提示を終えて三分過ぎにようやくテンポアップしてからは本流のようなアドリブが続く。そして形式上は再び冒頭のメロディに戻るわけだが、これはむしろ“第二テーマ”と呼びたくなるほど異なったニュアンスを持つものだ」。
この分析からも、また既述二作品の特徴からもわかるように、レッドの楽曲はまず①構成的な側面が強く、そこに②どのように自由にアドリブを展開させるかがもう一つのポイントとなる。ジャズ史的に概観すると①が作曲家によって意識され過ぎると「ウェスト・コースト・ジャズ」や「第三の流れ」のように窮屈なものになってしまうが、レッドの場合はむしろ①を隠し味程度に思わせるまでソロイスト(サックス奏者)に自由に歌わせる印象。ただしそれ故にこの時期の「ブルーノート」レーベル録音ピアニストの中で作曲家的側面がかえって埋没してしまった印象もある。まあ、こういう印象自体が「後づけ」の類であり、普通に音楽を聴いていれば②の側面が①を圧する勢いであってこそ「ハード・バップ」としか感じなかったのも当然だ。 結局レッドは本レーベルにはこれら二枚のみをリリースして去り、以後戻ることはなかった。ただし61年1月に最後のセッションが行われており、後年それも含めて「ザ・コンプリート・ブルーノート・レコーディングス・オブ・フレディ・レッド」“The Complete Blue Note Recordings of Freddie Redd”(Mosaic)が発売されてはいる。そして再演「ザ・コネクション」を報告した原田のコラム「JAZZ徒然草」では第54回(2010年2月25日)でレッドの復活ライヴの模様を伝えている。これも興味のある方は覗いてみて下さい。