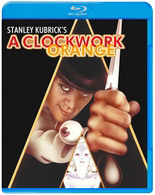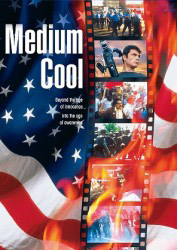海外版DVDを見てみた 第20回 ピーター・ワトキンスを見てみた Text by 吉田広明
近未来を扱う三作~『ウォー・ゲーム』、『傷だらけのアイドル』、『パニッシュメント・パーク』
『ウォー・ゲーム』War game(65)は、ヴェトナム戦争における緊張から、イギリス本土にソ連の核ミサイルが落とされた、という設定で描かれる。ヒロシマ、ナガサキへの原爆投下、ドレスデン等ドイツ各地への空爆の資料を駆使し、実際にイギリスに原爆が投下されたら何が起こるのかをシミュレートしている。識者のインタビュー、原爆の熱波や光線に逃げ惑う人々の生々しい(そう見える)映像など、これまでの手法が一層洗練された形で使用されている。記述が前後したが、59年の『無名兵士の日記』仕上げの時点でワトキンスはコマーシャル・フィルム製作会社に勤めており、その同僚に、後に映画史家、映画作家となるケヴィン・ブラウンローがいた。ブラウンローは既に当時一本の映画の製作にかかっており、ワトキンスもその映画を手伝っている。『それはここで起こった』(TV放映題『イギリスは占領された?』)It happened here(64)。ナチス・ドイツが第二次大戦に勝利し、イギリスを支配しているという設定のドラマで、アクション部分に関しては、ニュースリールのように手落ちカメラで撮られた臨場感あふれる撮影がなされているということだ(筆者未見)。架空の世界を、まるでそれが現実であるかのように、ドキュメンタリーとして撮る、というワトキンスの発想に、ブラウンローと共通するものがあるということは確かだろう。そしてこうした発想が生まれるに当たっては、イギリスが30年代以来、ドキュメンタリーに長けた国だったということもあるだろう。ドキュメンタリーは、現実を見、認識する術として、それ自体に疑念を抱かれることはなかったが、ブラウンローやワトキンスに至って、それ自体が反省の対象となった。ドキュメンタリーは自明に「リアル」なものではなくなる。
『傷だらけのアイドル』大衆を操るカリスマ歌手
『パニッシュメント・パーク』裁判
『パニッシュメント・パーク』殺される有罪者
さてワトキンスは、『ウォー・ゲーム』をスウェーデンで配給した業者に招かれ、その地で映画を製作する。『グラディエイター』The Gladiators(The Piece Game)(68)。これはアメリカでDVDになっているが筆者未見。いよいよ暴力的なものになってゆく世界が、その暴力衝動を発散させ、戦争を回避するため、各国代表が死を賭して戦うゲームが開かれた、という設定(副題の“平和ゲーム”はそれに由来)。ゲームという題材は次の『パニッシュメント・パーク』Punishment Park(70)にも引き継がれる。映画製作現在から一年後71年の近未来、ヴェトナム戦争による社会不安から、政府は平和主義者や懲役拒否者らを拘束、軍事基地内で彼らを秘密裏に裁判にかけ、有罪とされた者たちは、懲役に服するか、パニッシュメント・パークでのゲームに参加するかを選択することになる。そのゲームとは、砂漠を横断して数十マイル先にあるアメリカ国旗にたどり着けば恩赦が与えられる、というものだが、保安官、州兵などからなる武装した連中がジープで追いかけてくる。映画は、とあるグループの裁判の様子(といっても弁護人も証人もなく、被告と、明らかに保守的な傾向の陪審員がわめき合うだけだ)と、その前に裁かれたグループのパニッシュメント・パークでの追跡劇の交互のモンタージュから成る。裁判の場面ではズームが多用され、急に発言した発言者の方にカメラが向くなど臨場感が醸成される。追跡劇の方では、カメラは逃げる者、追跡する者双方に密着し、インタビューなどを交えながら双方の行動を追う。設定上は、イギリスのTV局が取材しており、ヨーロッパで放映される予定の番組。あまりに強権的で傲慢な追手たちに、カメラ・クルー自身が思わず激昂し、口論となる、といった場面までもが演出され、もし何の予備知識もなく見たならば、あるいはこれを現実と思い違う観客もいるかもしれないくらいだ。ワトキンス自身の立場が、反政府、反権力であることは疑いなく、しかしだからといってこれを反政府のプロパガンダと言ってしまうにはためらいを覚える。いくらリアルに見えようとも、これを事実起きていることと思わせる(その危険性は十分ありすぎるほどあったにせよ。また9.11以後のグアンタアモ基地での出来事は、この映画で描かれた裁判の現実化そのものだったわけであるが)ことに作者の意図があるとは思えず、こんなことが起こりかねない政治的現状に注意を促すことはまず間違いなく意図されていただろうけれど、それ以前に観る者の関心は、どうしてこのような手法が取られたのか、こうした作品を前にして、フィクションとドキュメンタリーの境界線はどこにあるのか、という疑問に向かうだろう。この答えのない疑問こそ、ワトキンスの作品群の達成した最良の成果と言える。
なお、『パニッシュメント・パーク』は、その頃ワトキンスと交流があり、共同企画の話もあったようであるハスケル・ウェクスラー(『カッコーの巣の上で』75、『帰郷』78など、いわゆるニュー・シネマを代表するカメラマン)の、やはり虚実の境界線を揺るがせる監督作『アメリカを斬る』(69)と問題意識を共有しているようである。フィクションとドキュメンタリーをめぐり、68年という時代が持っていた映画の可能性については遠山純生「見過ごされた発火点としての映画と一九六八年」(早稲田文学2005年一月号)を参照。