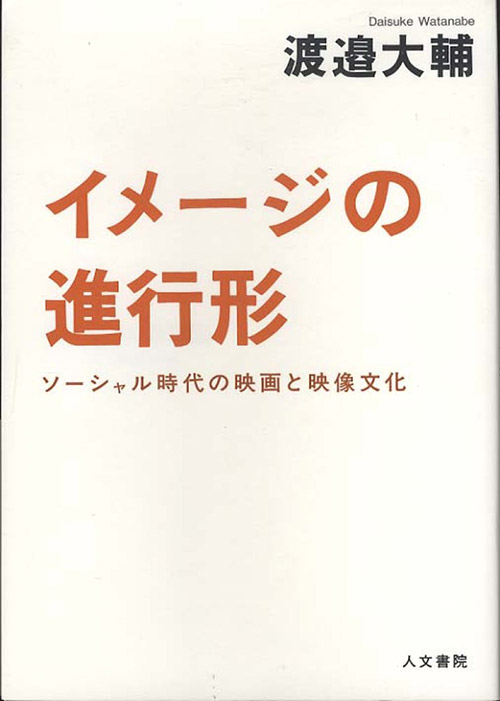海外版DVDを見てみた 第20回 ピーター・ワトキンスを見てみた Text by 吉田広明
『カロデン』
『忘れられた顔』を評価したBBCは、ワトキンスをディレクターとして招く。助監督を十八か月務めた後、長編製作の機会を与えられたワトキンスは、カンタベリーのプレイクラフト時代から持っていた企画を実現することにする。カロデンの戦いは、1746年に起こったジャコバイトとグレートブリテン王国軍の戦闘。ジャコバイトは、名誉革命後の反革命勢力で、自分たちが正当な王家であると主張、スコットランドのハイランドの氏族たちが主な支持者だったという。映画で見る限りジャコバイト軍には、ろくな装備もないし、チャールズ若僭王はじめジャコバイトの将校たちもさしたる作戦も持たなかったようで、グレートブリテンの指揮者カンバーランド公の率いる大砲隊にあっけなく蹴散らされてしまう。筆者には、この戦闘がイギリス史において持つ意味もあまり良く分かってはいないが、これはイギリス本土で戦われた最後の戦争ということだ。映画でも描かれるが、戦闘後、カンバーランド公は、負傷した兵士たちの首を刈らせ、その残虐さから公は「屠殺屋」と渾名されることになり、また戦闘後しばらくは平定の名のもとに残忍な残党狩りが行われ、加えて以後、キルトなどスコットランドの文化が抑圧されることになって、スコットランドのイングランドへの遺恨が根深く残ることになったという。こうした暴力への批判的なまなざしは、ワトキンスにおいて初期短編から一貫して継続される態度である。映画は、それぞれの大将、兵卒たちのインタビュー、戦いの実況中継(望遠鏡をのぞきながら実況中継する記者がいる)によって描かれる。ワトキンス自身が担当するナレーションが全体の状況を説明するが、例えば、グレートブリテン軍一兵卒の給与とカンバーランド公の給与の比較などのコメントなどはあくまで客観的なデータに過ぎないものの、それをあえて述べる辺りがアイロニカル。以前の短編と違って、砲撃の模様もアフレコの音声で処理されるわけではなく、特効で再現される。戦場にカメラを持ち込んだという設定で、現場の混乱そのままに、画面は揺らぎ、何が起こっているのかを把握するのも難しい。
ワトキンスによれば、18世紀の出来事を描くにあたって、20世紀のヴェトナム戦争のニュースリールの手法を用い、どこかで見たような親しさを感じさせ、またそのアナクロニズムによって、ジャンルの権威を揺るがせることを目論んだということだが、ワトキンスとしてはこの作品に、というか、このグレートブリテン軍の残酷さに、当時のヴェトナム戦争におけるアメリカ軍の残酷さを連想してもらいたかったようだ。そのように受け取ってもらえなかったことの不満をワトキンスは述べているが、やはりそれ以上に、この作品の手法に関心が集まってしまった、それだけこの手法はインパクトが強かった、ということだろう。実際この作品を見て、手法に関心を向けないわけにはいかないだろう。作品の内容もともかく、その作られ方に見る者の関心を向けさせるという意味でこの作品は、優れてメタ・ドキュメンタリー的な作品であるわけだ。
この作品で使われているリアリティ醸成の手法(手持ちカメラの揺れる映像、全体を把握させない限られた画角、荒削りな編集)は昨今の疑似ドキュメンタリーを連想させるものがある(ワトキンスのこれまでの作品にはあまり特徴的ではないが、臨場感のある音声も重要だろう)が、ワトキンスの時代と現在とでは、メディアの在り方が違っているので、これらを短絡的に結びつけるには注意を要する。ワトキンスの時代にあっては、そうした手法自体、TVのニュース映像によって用いられ始めた新たな手法であり、それを歴史再現劇に用いるということには、当時スペインなどで大バジェットの史劇を作り続けていた古典期的ハリウッドに対する批判の意味が込められていた。実のところハリウッド・スタジオも50年代を通して崩壊しつつあり、ワトキンスの批判の対象も実態を失っていこうとしていたのだが(とはいえ、それは70年代に回帰する)、それはともかく、また一方で、この作品はあからさまに時代錯誤を犯し、手法そのものを浮き上がらせることで、こうした手法を使えば、どんな出来事でもリアルに見えるのだ、として、手法そのものを批判しているようにも見えるのである。ワトキンス自身は、ハリウッド的な(具体的にはハイ・キー照明などを挙げており、ということはつまり古典期的な、ということであり、なおかつ今の目で見れば60年代的な批判の契機を失ったように見える70年代以降ハリウッドのマス映像もそこに含めてよかろうと思うが)映像を、MONOFORM(単一形態)とか、MAVM(mass audio-visual media)といった彼独自の造語によって批判しており、映像の在り方に強い批判意識を持つ作家だが、ハリウッド流の作法に対し、対抗手段を用いる、というだけでなく、その対抗手段自身にも疑いの目を向けてもいるのであって、その批判は周到だといわねばならない。
一方近年の疑似ドキュメンタリーは、簡便で高性能な映像記録媒体が普及し、しかもそれを何らかの理念によって「作品」にまで仕上げる意思を待つまでもなく即時的に人目に触れさせることのできる環境が整った時代の産物である。日常生活が常時映像として記録され、切れ切れのまま人目に晒され続けている。日常生活において既にそうした光景が当たり前である時代にあって、上記したような手法は、ワトキンスにおけるような批判ではなく、それこそ日常的に起こっている事態をなぞっているに過ぎない。と言っても疑似ドキュメンタリーを悪く言っているわけではなく、ワトキンスが『カロデン』を撮った時代のように最早対抗軸があるわけではない現状では、日常と映像世界の境目がなくなってしまったことそのものを、まずは認識する、という点に、今のところ疑似ドキュメンタリーの持つ意義があるものと思われる、ということだ。ワトキンスの作品と、近年の疑似ドキュメンタリーは、前者は当時のメディア批判であり、一方後者はメディアの現状認識であるという点で、持つ意味が違っている(疑似ドキュメンタリーを含む現在のイメージの総体については渡邉大輔『イメージの進行形』人文書院、参照)。
さて、過去に時代を設定し、あからさまな時代錯誤を犯して見せたワトキンスは、次に近未来を舞台に、同じ手法を用いて見せる。『ウォー・ゲーム』、『傷だらけのアイドル』、『パニッシュメント・パーク』の三作品である。