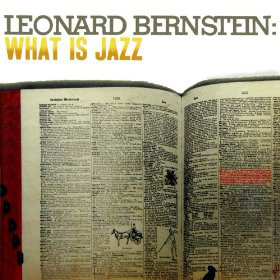映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第72回 「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」物語 その2
第72回 「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」物語 その2
アレンジャー、ギル・エヴァンスの貢献①
前回はラスト部分でマイルス・デイヴィスのアルバム「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」“Round About Midnight”(原盤COLUMBIA)につけられたジョージ・アヴァキャンのライナーノーツの一部を読みながら、そこに幾つかの「後述ポイント」をチェックしておいた。今数えてみると七つあった。まず列挙しておく。①セロニアス・モンク。②デューク・エリントン。③クーティ・ウィリアムズ。④ディジー・ガレスピー。⑤「人々が彼の安否を案じ始め出した頃」。⑥ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル。⑦「彼は復帰してはいたのだが、彼の演奏を耳にしたものはまだいなかったのである。」以上。これらの意味を記述することが当然今回からのテーマとなるのだが、順不同、また論述の自然な文脈の流れの中でそれぞれ触れていくことになろう。本アルバムはマイルスのメジャー宣言、つまり大手レコード会社コロムビアからのリリース第一弾である、と記しておいたが、彼をコロムビアに誘い、アルバムを制作したのが同社に所属するアヴァキャンであった。つまりプロデューサー自らがライナーを書いている。これは比較的珍しく、ジャケット裏の曲目下、一番目立つように「バイ・ジョージ・アヴァキャン」と記してある。やはりアヴァキャンとしてはマイルスと契約できてよほど嬉しかったのだろう。「本アルバムは米コロムビア・レコードにおけるマイルス・デイヴィスのデビューとなる作品である」とライナー冒頭にある。
それに続けて、こうも書く。「とはいえ、レナード・バーンスタインの講義と実演によるアルバム、『WHAT IS JAZZ』の〈SWEET SUE〉でもマイルスの解釈を聴くことができる。」これは正確には「スウィート・スー、ジャスト・ユー」“Sweet Sue,Just You”で、現在ではボーナス・トラックとしてCD盤「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」に収録されている。同じ日に一緒に録音し、異なるアルバムに振り分けたのだ。バーンスタインのアルバムはタイトルから類推されるように、ジャズの音楽的特質と魅力をバーンスタインならではの語り口で解説していく内容であり、別な角度からいずれ取り上げることもありそうだが、とりあえず今回はスルーしておく。
アヴァキャンのライナーの内容はマイルスのその時点でのキャリアから音楽的人脈、演奏スタイル、曲目解説までコンパクトにまとめる懇切丁寧なもので、全部紹介したいほど優れている。CDにはちゃんと日本語訳(堀池美香子訳)で全文掲載されているので是非読んでおいていただきたい。ライナーと言えば、日本盤CDにアヴァキャンに先だって掲載されている小川隆夫によるものも実に面白い。こちらは現在、小川によるマイルス伝「マイルス・デイヴィスの真実」(平凡社刊)でもほぼ同じ文章が読める。同書は、マイルスと親交のあった小川が、本人から直に聞きだした言葉をふんだんに盛り込んで構成しており、世界的に見ても類書のない極めてオリジナリティの高いものだ。また小川は医師としてのニューヨークでの留学生活や、帰国後のジャズ・ジャーナリストとしてのキャリアの折りにふれ、数多くのミュージシャン・インタビューを随時行ってその成果をも取り込んでいて、マイルスに関わったジャズマンの貴重な話も多く聞ける著書となった。
本アルバムにおけるギル・エヴァンスの役割について「あのアレンジはわたしのものだ」とギル自身が小川に語っている。さっそく引用する。
アルバム全体に関わったわけじゃないが、「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」“‘Round About Midnight”に関しては、わたしのアイディアが用いられている。もともとあのアレンジは、あるシンガーのために用意しておいたものなんだ。コルトレーンがテーマのバックで吹くカウンター・メロディは、本来オーケストラのためのものだったんだよ。(略)ホーンやブラスがあの低音部を演奏して、それをバックにシンガーがメロディを歌う。でもカウンター・メロディを使うアプローチは、マイルスも以前からやっていたと言っていたけれどね。(略)穏やかで繊細な感じのテーマが終了すると、一転してビッグ・バンドの迫力あるサウンドが例のヴァンプを演奏するんだ。それをマイルスは、コルトレーンとの二管でうまく表現していた。
このバージョンを読者の皆さまが既に聴いてあるものと仮定して話を進める。
引用は著書からだが、CD盤のライナーと比べると面白いことに気づく。ギル・エヴァンスはCD盤では「イントロからして私が書いたものだし」とも述べるのだが、著書「マイルス・デイヴィスの真実」ではこの一節が削除されているのである。これが書きもれじゃなくて意図的なものだとしたら、小川は、イントロ部が本当にギルの手によるオリジナルかどうかについては保留したことになる。あるいはその件は「コルトレーンがテーマのバックで」と述べる部分と重複するので「書きもれ」じゃなく、わざと排除したのかもしれない。こういうのは他の人が演奏したバージョンと聴き比べることで分かる。まあ分からないかもしれないが、とりあえず聴き比べのモチベーションにはなる。
そこで一曲、今度はマイルスの師匠のトランペッター、ディジー・ガレスピー(後述ポイント④)による「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」を聴いてみる。ユーチューブYou TUBEだと「ラウンド・ミッドナイト チャーリー・パーカー ディジー・ガレスピー」Round Midnight Charlie Parker Dizzy Gillespieのタイトルでアップされたものを聴くのが良い。附された資料コメントによれば録音月日は1951年3月31日、ニューヨークのクラブ「バードランド」からのラジオ放送(のアルバムから)の模様。MCはジャズ関連業界では特に有名なパーソナリティ・シンフォニー・シッドらしい。曲の紹介ではこの時代だからもちろんちゃんと「アバウト」を入れているが、上記のように、アップされたタイトルにはない。
そういうわけで聴いて欲しいのはイントロだ。ネット辞書によるとマイルスのバージョンはガレスピーを踏襲したとされている。本当だろうか。すると、ガレスピーも確かに印象的な深い孤独を感じさせるメロディをまず演奏し、マイルス版にちょっと似ているが、そこは根っから陽気なビバッパー・ディジー。なので、孤独の湖の底の底まで降りていく、といった雰囲気にはならず中途から技巧的な激しい上昇下降を繰り返す「いかにも」なディジー節(ぶし)に変わってしまう。これは別にディジーの悪口でもマイルスの悪口でもないが、マイルスにはもともと極端にアクロバティックな技巧の誇示はやる気もないし、出来なかった可能性だってある。一方ディジー。彼にはこの曲に対して、マイルスがやったような孤独感の表出だけで全体を統御する、という音楽的発想がそもそもない。そういう時代の人なのだ。しかし、彼としても「この時代この曲」を演奏するにはある種のスタイリッシュな演出が必要であることは十分承知していたから、わざわざ原曲にないイントロを加えたのだ。で、とりあえずの結論。このイントロの演出はディジーのオリジナルをアレンジャーのギルと演奏者のマイルスが深めた、つまり孤独感を徹底させたものである。徹底させたら逆にシンプルになってしまったわけで、こういうところが音楽表現の(というかギル・エヴァンスのアレンジの)面白いところだ。
ネットで同時にアップされているディジーとフィル・ウッズとの共演盤による「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」Dizzy Gillespie & Phill Woods Quintet Round Midnightをついでに聴いてみると、今度は彼の方がマイルスから逆に影響されているのも分かる。ずっと後年の演奏だからで、こういうことはよくある。また一つ特記すべきはオリジナル・イントロ同様に、エンディングの工夫(原曲メロディ終了後、トランペットが即興風にメロディを軽く吹く)もディジーが始めたという点だ。こちらはマイルスもかなりきちんと踏まえている。つまりセロニアス・モンク(後述ポイント①)作曲による原曲のメロディを演奏する際の枠組み(前奏部と終結部)をディジーが創案したと言って良い。この点は後ほど総括する。