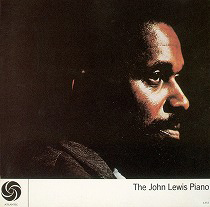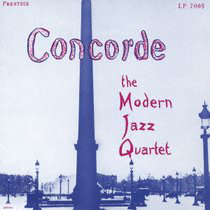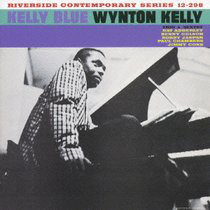映画の中のジャズ、ジャズの中の映画 Text by 上島春彦
第46回 60年代日本映画からジャズを聴く その7
アレンジャー八木正生の映画音楽集とスタンダード集をちらっとだけ
第46回 60年代日本映画からジャズを聴く その7
アレンジャー八木正生の映画音楽集とスタンダード集をちらっとだけ
ジョン・ルイス風アレンジが斬新な八木の「ブルー・ムード」ジャズ
八木正生の1970年代のアルバム「インガ」も近々初CD化されるという情報が入ったけれども、まだ正式リリースされていないようなのでこの件はお楽しみということで。代わりに今回は近年CD化された「モダン・ジャズ・ブルー・ムード」(コロンビア)から入りたい。こちらは「八木正生と彼のグループ」による65年作品。元は当然LPで、一枚に12曲のスタンダード・ナンバーが収められている、ということは一曲あたりの演奏時間も二分から三分台がほとんど。ジャズとしてはアドリブ展開が物足りないのだが、アレンジャーとしての八木の本領は発揮されている。編成は八木の当時のレギュラー・トリオ(ベースに寺川正興、ギターに小西徹)を中心にしながらサックス(またはフルート)、トランペット、ドラムスが適宜加わる豪華版。解説にも「ジャズ・ファンは勿論のこと、ポピュラー・ファンにも快くひびくサウンズと雰囲気」とあり、いわゆる「バック・グラウンド・ミュージック(BGM)」的ムード音楽として機能していたもののようだ。こういうタイプのアルバムはもう存在しないからそれだけで嬉しくなってしまう。60年代から70年代に人気を博した、ジャズ系BGM(「クロスオーバー」とか「フュージョン」とかじゃなく、バラード中心で若者向けというより大人のための静かな音楽)にはテナー・サックスが欠かせなかった。それでこのアルバムでもトップの「クライ・ミー・ア・リヴァー」“Cry Me a River”には宮沢昭のそれっぽい「むせび泣く」テナーがフィーチャーされているわけだが、アルバムのポイントはむしろ八木のアレンジにおける小西のギターである。正確に言えばギター、及びギターを盛りたてるピアノとベースの上品さ。インタープレイと言って良いのだが音数をそれぞれが節約している感じ、つまり「引き算」のインタープレイだ。
プレヴィンはかつてドラマー、シェリー・マンの大ヒットアルバム「マイ・フェア・レディ」“My Fair Lady”(Contemporary)で同じナンバーをピアノ・トリオで演奏した時とアプローチを変えて、テンポは「ミディアム・ファーストを採用しロマンティックなアドリブをともなった可憐なアレンジが展開される(木下浩二のライナーノーツより)。」ただし軍配は前回の方に上るのではないかと思う。意図的に普通のテンポにした結果、何もかもが普通の感じだ。プレヴィンの「カクテル・ピアノ」含め。一方、八木盤はライナー執筆者、岩浪洋三の書くように「ジョン・ルイスを思わせる点描風なソロがスリリング」な好演。冒頭の「クライ・ミー・ア・リヴァー」を聴くだけではよくわからないのだが、二曲目以降は明らかにジョン・ルイスにインスパイアされたアレンジで、それがとても効いている。
ルイスはMJQのアレンジャー兼ピアニストとして知られるが、MJQを離れるとまた一味ちがった魅力を発揮する。その際のポイントが実はギタリストの採用であった。「ジョン・ルイス・ピアノ」“The John Lewis Piano”(Atlantic)と「グランド・エンカウンター」“Grand Encounter”(Pacific)がその典型で、ジム・ホールやバリー・ガルブレイスを起用して明るい音色を強調している。後者における「恋をしたみたい」“Almost Like Being in Love”のジャズ史に残る爽やかなイントロは八木盤の「木の葉の子守唄」“Lullaby of the Leaves”にもさりげなく影響を与えているようだ。即ち本盤の八木トリオは軽さが命。そうなると最初と最後の二曲でフィーチャーされる宮沢のテナーがやけに重く、かえって陳腐な印象を発せざるを得ない。この二曲以外で宮沢はフルートを吹いており、それがとても爽やかなだけに惜しい感じがするのだった。もっともそういう身勝手な感想は今だからこそ思うことで、既述のように「むせび泣くテナー」というのが当時この手のアルバムの最大の聴かせ所であったわけだ。
一応「クライ・ミー・ア・リヴァー」にもふれておくと、この曲は映画『女はそれを我慢できない』“The Girl Can’t Help It”(フランク・タシュリン監督、57)で「幻影の女」(そういう映画的設定の)ジュリー・ロンドンが歌って評判を呼んだもの。映画は全くの喜劇なのに彼女の登場場面だけ深刻で、そのミスマッチが抱腹絶倒という仕掛けである。映画自体はジャズというより初期ロックンロール満載。最近DVDが出たからプロモーション・ビデオ感覚で楽しんで下さい。またこのナンバーはアルバム「彼女の名はジュリー Vol.1&2」“Julie Is Her Name Vol.1&2 ”(Liberty)(LPでは二枚別々に出たがCDでは一枚)冒頭に収録されている。アルバム解説によると56年に「ヒット・チャート20週連続トップのミリオン・セラーを記録」とある。映画版がオリジナルじゃなかった。
もう一曲、面白いナンバー「朝日のようにさわやかに」“Softly, as in a Morning Sunrise”を紹介したい。ミュージカル「ニュー・ムーン」から生まれたこのスタンダードはMJQのアルバム「コンコルド」“Concorde”(Prestige)他で演奏され、いわばMJQの代名詞的存在となっているのだが、八木は自身のアルバムにこれを入れるにあたってわざわざ「MJQ風ではない」アレンジを採用する。ピアノ奏法はシングル・トーンを多用することで「ジョン・ルイス風」に聴こえるにも拘わらず、である。このバージョンのインスピレーション源はひょっとするとジョン・ルイスではなくウィントン・ケリーの「ケリー・ブルー」“Kelly Blue”(Riverside)かも知れない。またジョージ大塚のドラムス(正確にはベルとシンバル)がリードする曲への入り方は確かにMJQのドラマー、コニー・ケイを彷彿とさせるものの、そこはかとなく「ピンクパンサーのテーマ」“The Pink Panther’s Theme”っぽさもある。アニメーション同様すっかりおなじみになったナンバーは、後年有名になったキャラがアニメとして独立する以前の64年に映画『ピンクの豹』“The Pink Panther”(ブレーク・エドワーズ監督)の主題曲としてヘンリー・マンシーニによって作られたものだったから時代的には符合する。つまり、どうやらアレンジャーとしての八木正生はこの一曲を「ジョン・ルイス風でありながら、かつMJQ風でなく」仕上げるため、ウィントン・ケリーやヘンリー・マンシーニのスタイルを経由するという軽業を演じているのであった。